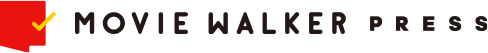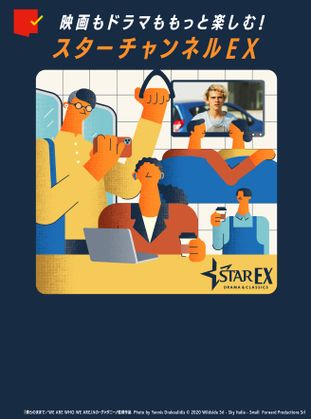『関心領域』ジョナサン・グレイザー監督ら、独特の手法に込めた意図明かす「目で観るのではなく、耳で聴く映画」「頭で考えるのではなく、身体でずっしりと感じる映画」
第96回アカデミー賞で国際長編映画賞と音響賞を受賞した映画『関心領域』(5月24日公開)のトーク付き特別試写会が5月15日にユーロライブで開催され、ジョナサン・グレイザー監督、音楽のミカ・レヴィ、プロデューサーのジェームズ・ウィルソンがオンラインで出席。上映後の会場からの質問に答えた。
イギリスの作家マーティン・エイミスの同名小説を原案に、『アンダー・ザ・スキン 種の捕食』(13)のグレイザー監督が10年もの歳月をかけて映画化した本作。1945年を舞台に、アウシュビッツ強制収容所と壁一枚を隔てた屋敷に住む収容所の所長、ルドルフ・ヘス(クリスティアン・フリーデル)とその妻ヘドウィグ(ザンドラ・ヒュラー)ら幸せに暮らす家族の姿を描く。
上映後の会場からは、さまざまな質問が上がった。「役者さんの表情に影がかかっていたりと、その表情があまり見えないように丁寧な撮り方をしているように感じた。その意図は?」と被写体との距離について問われると、グレイザー監督は「おっしゃるように、意図的にそういう演出をしています」とコメント。
「壁にへばりついているハエのように、登場人物たちを観察するような映画にしたかった。観客にひたすらキャラクターたちの行動、やり取り、身体の動かし方を見つめてもらうような映画。私自身、役者の芝居を見ているのではなく、実在する人物をドキュメンタリーのように撮っている感覚を覚えたかったので、そういう演出をしています」と、登場人物たちを傍観することを心がけて取り組んだという。
またセットのなかに最大10台の固定カメラを仕掛けて、異なる部屋のシーンを同時に撮影するという独特の制作方法も採用している。グレイザー監督のビジョンを具現化するために「綿密にプランを立てて撮影に入った」というプロデューサーのウィルソンは、「その狙いは、観客の皆さんに、いまこの家族がここに生きているんだ、それを我々は身近で見ているんだ、いままさに起きていることなんだという感覚を味わってほしかった。うまくいったのではないかと思っています」と目指したものについて語った。
家族の暮らしと壁ひとつ隔てたアウシュビッツ収容所の存在が、音や気配から伝わってくるのが本作の大きな特徴だ。観客からは「冒頭から、真っ暗闇の状態が続く。その間に悲鳴が聴こえてくる。真っ暗闇の場面も印象的だった」という感想もあった。音楽を担ったレヴィは「真っ暗闇のなかでいきなり音を聴かせるというのは、ちょっと奇妙な感じがしますよね」と切り出し、「目で観る映画ではなく、むしろ耳で聴く映画」と本作を表現。「監督には『聞き耳を立ててほしい』という意図があって、冒頭でひたすら音を聴かせています。観客の耳が慣らされてきたら、今度はサウンドデザインに耳をそばだてるように設計しています。私たちは、映画のなかで繰り広げられている暴力を見ることはできないけれど、耳で拾うことができる。そうやって誘うように、音をデザインしました」と聴こえてくる些細な音にも、観客が集中するようなアイデアが込められているという。
「いつかホロコーストに関する映画を撮りたいと思っていた」というグレイザー監督。「これまでもホロコーストに関する映画はたくさん作られていますが、そのどれにも似ていない映画にしたかった。加害者側の視点から見えるものを描きたいと思っていた」と着想について語り、「『80年前の出来事です。歴史ものです』『現代とは関係ないものです』というものにはしたくなかった。なぜ我々は学んでこなかったのか。なぜ同じ過ちを繰り返すのか。いまの世の中、現代に訴えられるような作品にしたかった」と本作に込めた想いを吐露した。
いまも世界各地で争いが起きているが、グレイザー監督は「私たちは、世の中で起きていることに対して対峙することを避けるところがある。それは安心、安全な領域で過ごしていたいから」と無関心の恐ろしさについて言及。「本作では、黙認することがどこに行き着くのかという、極端な例を示したつもりです。劇中の野心あふれるブルジョア一家のなかに自分を見出したとすれば、黙認や共犯関係が進むと最終的にどこへ行き着くのかについて、合点がいくのではないかと思う。本作は頭で考えるのではなく、身体でずっしりと感じる映画。毒を含んだ果物を一口、食べたような苦味を感じてほしい」と力を込め、「黙認や共犯というのは、私たち一人一人が拒否する力を持っている」とメッセージを送っていた。
取材・文/成田おり枝