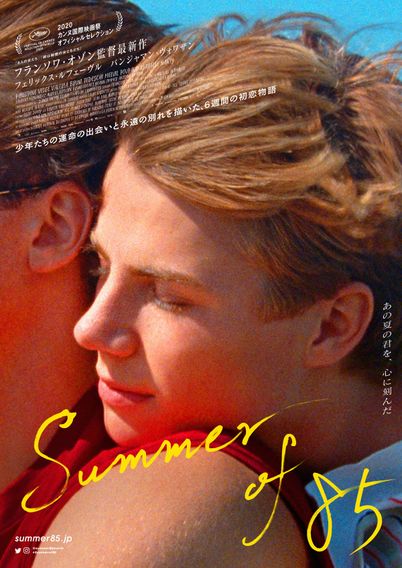フランソワ・オゾン監督が語る、35年をかけ作り上げた『Summer of 85』への想いとインスピレーションの源
「誰もが見てこれは私の話だと感じる、ユニバーサルな物語を描きたかった」
劇中には、ウォッシュアウトのジーンズ&バンダナに代表されるファッションは勿論、ダヴィドがアレックスの頭に“ウォークマン”のヘッドフォンをかけて音楽を聴かせるシーンとか、1980年代に流行った1980年代カルチャーが至るところに溢れ返っている。「ウォークマンは原作にはないシーンで、撮影監督に頼んでいたストロボが現場に届くまでの間に、たまたま思いついたアドリブなんです。当時、ウォークマンはフランスでも大流行していて、好きな子の頭にヘッドフォンをかけるというのは、若者たちにとってとてもロマンチックな行為だったんですよ」。
全編に流れるTHE CUREの「In Between Days」や、ロッド・スチュアートの大ヒット曲「Sailing」や、バナナラマの「クルーエル・サマー(ちぎれたハート)」など、音楽も1970~80年代のヒットチューンで固められている。「僕が思春期にハマっていた曲ばかりです。ブリティッシュ・ニューウェイブが大好きだったんですよ。でも、映画に使ったのは単なるノスタルジーばかりではなく、それらの曲がエネルギッシュであると同時にメランコリックで、10代の感覚にピッタリだったからです。キラキラした生命感に溢れている一方で、どことなく物悲しさを漂わせているという、失われた少年時代へのオマージュを選曲には込めたつもりです。それに、歌詞が平凡でどんなストーリーにも当てはまるから(笑)」。
特に近年、セクシュアル・マイノリティに対する社会の理解は深まり、それと共に、映画の表現も進化したと言えるのだろうか。「まず、セクシュアル・マイノリティを描く映画が増えて来ましたよね。それはとてもいいことだと思います。開かれた精神を持った人が増えて来たのでしょう。一方で、まだまだ同性愛者に対する社会の偏見は根強いものがあり、いまも世界のどこかでは同性愛そのものが禁止され、罰せられたりもしている。本当に痛ましく絶対にあってはならないことです。どんな恋愛感情も生かしてあげるのが健全な社会の在り方ではないですか。そんななかで、映画ではせめて彼らにポジティプであって欲しいと願うばかりです。それは政治的な観点から見てもいいことだと思う。自分自身がどういう人間かということを隠すのではなく、主張できる社会を目指すのは」。
だからと言って、監督は「プロパガンダのために映画を撮ったりはしない」と断言する。「今回の場合も、LGBTQという要素は意識せず、ユニバーサルな恋愛映画を撮ったつもりです。アレックスとダヴィドはたまたまどちらも男性ですが、別に女性同士だろうが、男女でもよかった。それが僕にとっては美しいし、自然なことだと思っているから。そうしたらどうでしょう?フランスで公開したら、観客のメインは若い女の子だったんですよ。誰もが見て、これは私の話だと感じるユニバーサルな物語を描きたいという僕の願いは、劇場で叶えられたというわけです」。
映画のなかに印象的な言葉がある。それは、「人生とはすべて物語に置き換えられる」というものだが、オゾン監督の場合は「映画に置き換えられる」と変換できるだろうか。「いや、そんな風に考えたことはないです。ただ言えるのは、僕はインスピレーションが枯渇したことがないということです。まわりのみんなは、なぜそんなにハイペースで映画が撮れるのか不思議がるけれど、インスピレーションってどこにでもあるんです。新聞や雑誌、街で通りすがる人々の会話のなかにもね。だから、実のところ僕にとってインスピレーションが大事なのではなく、最低でも3年の月日が費やせる作品があり、それをどうしても撮りたいという欲求があるかどうか?そっちの方がよっぽど大事なんです!」。
取材・文/清藤秀人