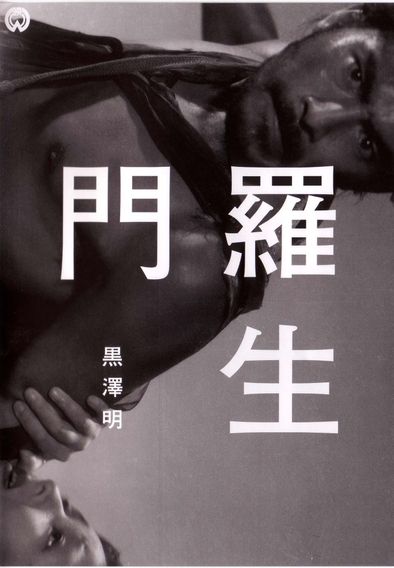M.ナイト・シャマラン監督が明かす、オリジナル作品を撮り続ける理由「劇場での映画体験は、ほかの手段では再現できない」
フランスのグラフィックノベルを翻案した、M.ナイト・シャマラン監督の最新作『オールド』(公開中)は、シャマランが得意とする、数奇な運命に巡り合った家族の物語だ。パンデミック以降では最初に撮影されたハリウッドの大作映画であり、多様性のあるキャスティングも見どころの一つとなっている。スリラー映画の大家であり、世界中のファンがその動向に注目するシャマラン監督に、独占ロングインタビューを行なった。
『オールド』では、急速で時間が過ぎていく美しいビーチに幽閉された人々が“老い”の恐怖に苛まれる。ビーチ・リゾートを訪れたガイ(ガエル・ガルシア・ベルナル)とプリスカ(ヴィッキー・クリーブス)ら一家は、ビーチでさまざまな怪奇現象に見舞われる。急速に成長する子どもたち、マドックス(トーマシン・マッケンジー)とトレント(アレックス・ウルフ)。海岸に打ち上げられた死体とパニックに陥る人々。彼らはこのビーチから抜けだすことができるのだろうか。
「リモートでのオーディションには、1000人以上が集まってくれたんです」
――今作のキャスティング作業はすべてオンラインだったため、これまでにない経験だったと聞いています。どのように行われたのでしょうか?
「ハリウッドで映画製作を再開したのは私たちが初めてでしたし、ヴァーチャルでのキャスティングも初の試みだったので、本当に奇妙な感じでした。いまとなっては当たり前のことですが、ベッドルームやキッチンにいる人々の姿を見るのも、自分のそんな姿を見せるのも異様な感じがしたし、俳優たちがリビングルームで演技をしているのを見るのも初めてのことでした。通常はキャスティング・ディレクター宛てに映像が送られ、それを元にキャスティングを開始するからです。しかし、良いこともありました。場所を問わずに選考ができるので、世界中から本当にたくさんの俳優がオーディションに集まってきたんです。『どうせ家に籠もっているし、シャマランが新しい映画のキャストを募集しているならやってみるか』という人が1000人以上も集まったんです。おかげで多様性に富んだキャストが揃ったので、本当に時間をかけて適切な組み合わせを考えることができました」
――この映画のなかで多様性のある家族やグループを描くことには、どのような挑戦がありましたか?
「物語の舞台がリゾート地であることから、同じ国や地域の出身に限らずに出演者を集めることができる珍しい機会でした。世界と私たちは、自分とは少し異なる人々や、自分とは異なる響きを持つ言葉を話す人々を見ることに、いままでよりも少しだけ寛容になっていると感じています。メキシコ人俳優を主役にした映画のなかで最大規模の作品がなにかはわかりませんが、『オールド』はその上位に位置するはずです。例えば、プリスカを演じたヴィッキーは、ドイツ語訛りの英語を話しています。このような要素はスタジオの要望で仕方なくやったわけではなく、物語や設定に沿ったものだったので本当に楽しむことができました」
――あなたが映画を作り始めた頃と比べると、いまのハリウッドは変化の途中にあると思います。その変化をどう捉えていますか?
「映画作りとはなにかと考えると、登場人物に共感してもらうことなのではないかと思います。25年前には、例えば黒人のキャラクターをライバルとして描いたり、主人公を楽しませる相棒として描くことはできても、観客自身を投影し、夫として、父親として共感してもらうのはとても難しいことで、長い間デンゼル・ワシントンだけがこの例外でした。それがいまでは、まだ完全ではないものの、どんどん変化が進んできています。女性の描かれ方に関しても、女性主人公の葛藤や強さを、当たり前に受け入れてもらえるようになってきたと思います。だから、これまでよりも自由なキャスティングをできるようになったと感じています」
「長年、人間ドラマとジャンル映画の融合を目指してきました」
――シャマラン作品に対する観客の期待は常に高いところにありますね。その期待を裏切らないようにする方法は?
「観客との間には非常に強い関係が結べていると感じています。作家と観客が強い関係を築く時はいつもそうですが、観客は期待して待ってくれています。例えば私がアガサ・クリスティの小説を手に取るときもそうです。小説の内容に期待し、キャラクターにも、ミステリーにも、すべてに期待値を上げています。だからこそ、私は観客が望むものを理解しようとしているつもりですし、彼らを満足させつつ、作家として成長するために様々なことに挑戦しているのです」
――世界には、実に多くのタイプのスリラー映画があります。あなたの映画の特徴や、あなた自身の得意分野はなんだと思いますか?
「私は、人間ドラマとジャンル映画の融合を目指してきましたが、それはとても難しいことでした。なぜなら、自分の家庭環境や家族と共通点があると思わせたうえで、超自然的な要素を混在させないといけないからです。なので、物語のジャンルを変化させる際は慎重になるようにしています。物語が進んでいくなかで、より怖い方向へと進んでいくことはできますが、逆戻りすることはできません。人間ドラマから、ミステリー、スリラー、超常現象スリラーのように、段階を踏んでジャンルを変化させていく必要があるのです。私は映画を作りながら、これらのルールがなんであるかを学んできました。また、宗教について直接言及することはなくとも、スピリチュアルな要素も少しずつ入れてきたつもりです」
――『オールド』の物語における、ジャンルの変化について教えていだけますか?
「本作では人間ドラマからSF、そのほかのジャンルへと変わっていくなかにロマンスの要素を並置すると、どう相互作用するのかに興味がありました。私は学校などで映画の構造について勉強したわけではありませんので、これは直感的に挑戦したいものであって、フリージャズを演奏するような感じなんだろうと思います。自分の耳に心地よいと感じる様々な形式や動きを試してみるようなものですね」
――監督自身がカメオで演じられる役は、脚本を書いている段階で決めているのですか?
「選ぶのは後からです。脚本を書いている時には、今回は入るところがないなと思っていても、何度か改稿を重ねるうちに、『ああ、この役を演じることができるかもしれない』と思うことがあります。こういう遊びは楽しいですが、私が出演する代わりに誰かを降板させているわけではないですよ(笑)。だいたいは映画の序盤で登場するようにしていて、観客の邪魔にならないようにしています。今回の『オールド』での役はとても楽しかったです。南の島が舞台なので、私のような外見でも普通にいそうな人に見えますしね」