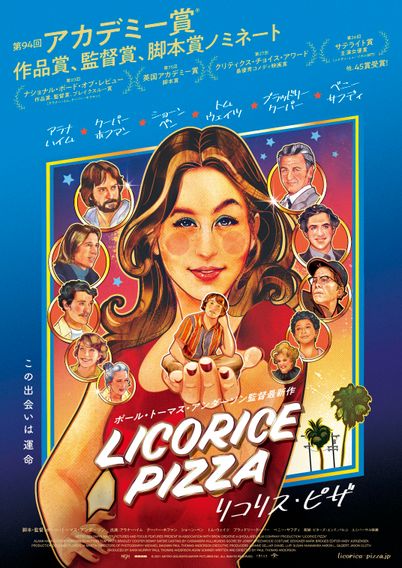ポール・トーマス・アンダーソン監督が語る、映画を作り続ける理由「映画が脳裏から離れたことはない」
「コロナ禍には、救命ボートの中で作っているような、ある種の焦燥感があった」
――私たちが実際には見ていない、経験していないサンフェルナンド・バレーの70年代の空気が伝わってくるような映像体験でした。
「できるだけ本物らしく見てもらえるように気をつけたので、そうだといいんですけど。なかにはほかの時代より簡単な時もありますが、ある時代を再現しようとするのは常にチャレンジングです。でも、バレーは当時とそんなに変わっていなくて、郊外の小さな田舎町という感じなんです。ちゃんと時間をかけて探せば、当時の建築物に近いものを見つけることができます。とはいえ70年代の風景は二番目で、ティーンエイジャーや周りの人々の見た目や行動など、彼らの間のダイナミズムがもっとも重要でした。僕の子どもたちや彼らの友達など、たくさんのすばらしいティーンエイジャーたちに出会いました。彼らの姿を写真に撮ると、1972年の子どもたちのように髪を伸ばしていて、その時代の短いスカートのような衣装を着ていて、まるで当時の卒業アルバムから抜け出てきたように見えるんですよ」
――この数年のパンデミックの間、子どもたちに対して申し訳ない気分になっていました。高校生にとって一生に一度のプロムなのに、その思い出もなく時間だけが過ぎていく。でもこの映画を観たあとに、彼らのレジリエンスを過小評価していたと反省しました。
「それはとても興味深い見解ですね。ここ数年の出来事から、いまの10代の子どもたちに感傷的な思いを抱くのはとてもよくわかります。僕の家にもその年頃の子どもたちがいるけれど、とても、とても大変でした。なにより、彼らがつらそうだった。僕らの歳とは時間の経過が違うんです。僕らは『3か月、1年なんてたいしたことない』と言ってしまいますが、彼らにとっての1年は一生分のようなもの。彼らは人と触れ合うことを恋しがっていました。
2020年末のパンデミックの真最中に撮影を開始した時、それが顕著に現れていたと思います。エキストラ役の子どもたちをピンボールパレスのセットに集めて、1週間ほど撮影をしました。自宅隔離から解放されて映画のセットに行けるということで、彼らの顔は興奮でとても輝いていましたが、彼らが参加しているのは、いまの彼らの日常から失われてしまったものでした。近所にピンボールパレスもなければ、パンデミックで友達と遊びに行くこともできない。撮影中は携帯電話を持たないでいてもらったので、みんなが同じ場所にいて、まるで違う時代にいるように振る舞ってくれました。彼らも衣装を気に入り、仲間との連帯感があってピンボールマシンで遊べる、映画撮影の環境全体を気に入ってくれました。そして、年上の僕らに向かって『とても楽しいです。いい時代だったんですね』と言ってくれました。少なくとも撮影の1週間は、実際に触れ合える機会を彼らに提供できてよかったと思います。彼らの愛すべきエキサイティングなエネルギーがシーンにも現れていて、映画からも感じていただけると思います」
――パンデミック中の撮影ということで、いままでの映画作りともっとも違ったのはどんなことでしたか?
「毎日テストをして、ずっとマスクをしているのは大きな違いですが…『この状況下で撮られた映画はいままでの映画と同じと言えるのだろうか?』と、ずっと自問自答していました。脚本も変えず、シーンもキャストもパンデミック前に計画していた通りに撮影しました。パンデミックのDNAが余計な要素として作品に入り込んでいることは否定できません。この環境でも撮影ができて幸運だ、一緒に作品が作れて光栄だという気持ちと共に、時計の針が常に動いていて、なにが起きるかわからないという緊張感も含まれています。救命ボートの中でなにかを作っているような、ある種の焦燥感や即時性がありました。
いま振り返るとおもしろいと思えますが、僕らは映画の撮影を再開した最初のグループで、みんな緊張していたし、その緊張したエネルギーが作品に注ぎ込まれています。それが映画にもいい影響を与えていると思います。パンデミック真っ只なかにいた私たちは、映画を再び作れる状況に感謝の気持ちでいっぱいになりました。これから20年、25年後にこの作品について再度考察した時に、同じ気分が感じられるかどうかはわからないけれど、その感じが残っていたらいいなと思います」
「映画が脳裏から離れたことはない。答えなんてないと思うからです」
――『リコリス・ピザ』では、脚本、演出、プロデューザー、そして撮影監督も務めています。映画作りのなかで、もっとも楽しんでいるのはどの職種ですか?
「この映画に関して言うと、演出ですね。というのは、今作には僕の家族や友達、とても親しい人たちが大勢関わっているから。そうした人々が一堂に会したことは、とても大きな喜びでした。僕は自分のオフィスに行って一人で脚本を書いているので、みんなが集まる撮影は純粋に楽しい時間です。編集もとても楽しかったですね。オフィスや家で編集をしていると家族が訪ねてきて、編集作業の一部になります。クリエイティブで、すばらしい瞬間でした」
――アンダーソン監督の作品には、ロサンゼルスの基幹産業でもある映画・映像産業がよく出てきますが、その理由を考えたことはありますか?
「立ち止まって、改めて自分がなぜ映画産業に惹かれるのか考えたことはないです。ただ自分が置かれた環境だと受け止めています。映画が脳裏から離れたことはありません。だって、答えなんてないと思うから。これが僕の関心事で、これ以外のことに時間を割くことはできません。これが僕の生きる世界、僕が好きな世界であり、だから映画作りに没頭しているんだと思います」