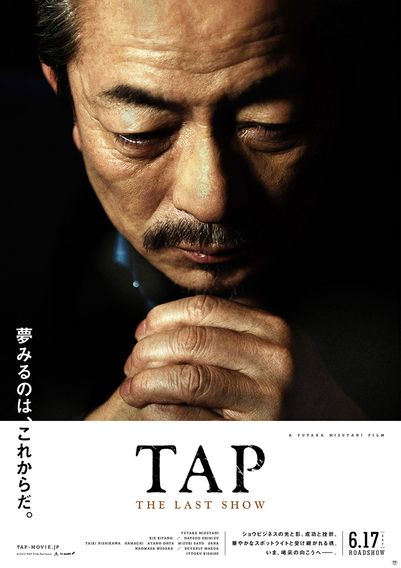【レビュー】“映画作家”水谷豊の挑戦 ――『轢き逃げ 最高の最悪な日』アクロバチックな語り口で謳い上げる人間賛歌
半世紀以上のキャリアをもち、名実ともに日本を代表する俳優といえる水谷豊。現在絶賛公開中の監督第2作『轢き逃げ 最高の最悪な日』では、初となる脚本も担当し、サスペンスフルな展開のなかに密度の濃い極限の人間ドラマを作りあげた。
20年近く継続中である近年の代表作「相棒」はもちろん、「傷だらけの天使」(74)、『幸福』(81)など多くのサスペンスやミステリーで名作を残してきた水谷がオリジナル脚本で描き切った本作を、映画プロデューサーとして活躍後、『見えないほどの遠くの空を』(11)で映画監督デビュー。社会現象となった『カメラを止めるな!』(17)にも脚本指導として携わり、現在、小説家としての代表シリーズ第3作「ワルキューレ 巡査長 真行寺弘道」(中公文庫)が好評を博している榎本憲男氏に、本作の物語構造が持つアクロバチックな魅力を解き明かしてもらった。
本作の物語は、ある地方都市で起きた交通事故で一人の女性が命を落とし、轢き逃げ事件へと変わるところから始まる。車を運転していた青年、宗方秀一と助手席に乗っていた親友、森田輝。二人は秀一の結婚式の打合せに急いでいた。婚約者は大手ゼネコン副社長の娘・白河早苗。悲しみにくれる被害者の両親、時山光央と千鶴子。事件を担当するベテラン刑事の柳公三郎と新米刑事の前田俊。それぞれの人生が複雑に絡み合うなかで事件は解決したかに見えたが、「真相」はまだ深い闇のなかにあった…。
※以下の文章には、詳細を避けつつも物語の核心に触れる部分がございます。
なんの予備知識もなく劇場に向かい、エンドクレジットを見て、本作が原作のないオリジナル脚本で、その執筆を水谷豊自身が担当していることを知って驚いた。
これは個人的な印象によるものだということを先に断っておくが、他業種から監督業に挑戦した場合、成功例がもっとも多いのが俳優である。その理由を推察すると、俳優は撮影現場に立つ機会が当然多く、たとえば脚本家や小説家や音楽家などよりも、撮影現場のシステムを体得していて、さらに演出される機会が多い故に、自分が演出する側に立った場合には、どのように俳優をコントロールすればいいかが分かっているからだ、そのような理由がとりあえず挙げられる。後者などは、専業の監督よりも有利な点を持っているとさえ言えるだろう。
しかし、こと脚本については、プロを雇ったり、数あるシナリオの中から自分に合ったものをチョイスする場合が一般的だと思う。クリント・イーストウッドはその代表だろう。特に、クライムストーリーはプロの技術が要求される傾向が強い。さらにプロのシナリオライターであっても原作なしで書くのは、手口の考案など難題に挑戦しなければならなくなる。となると、プロのシナリオライターの力はぜひとも欲しいはずなのだが…。だから、「脚本監督 水谷豊」というクレジットを見た時には、ちょっと驚いた。
もう一つ、日本映画におけるクライムストーリーには、ある種の傾向があることも先に述べておきたい。それは、犯罪の全貌が明らかになった時、あるいは犯人が捕捉される時に、観客の心に哀れに思う感情が醸しだされるということである。これは松本清張原作作品によって確立された傾向だ。橋本忍、山田洋次脚本、野村芳太郎監督の『砂の器』(74)や、橋本忍脚本、野村芳太郎監督の『張り込み』(58)がまさにその代表作と言えるだろう。以後、さまざまな日本の犯罪映画がこの路線を開拓してきた。おそらく水谷豊もここをストライクゾーンと定めて球を投げてくるのではないかと僕は内心どこかで思っていたのである。しかし、結果としては、本作はかなり予想外のものとなっていた。これもまた驚いた。実にアクロバチックな語り口に挑戦しているのである。
『轢き逃げ 最高の最悪な日』は、話が進展すると節目節目でその焦点(セントラル・クエスチョン)がズレていく。ズレていくのだが、そのエネルギーは減じることなく、ストーリーは前へと進んでいく。これが本作の特徴である。
冒頭、友人を助手席に乗せて、婚約者との待ち合わせに遅れまいと車を飛ばしていた若い男が、若い女性を跳ねてしまい、あろうことかそのまま逃走し、のちにニュースで彼女の死を知ることになる。こうなると観客は当然、主人公然として登場した若い男にある程度気持ちがシンクロしていたから、「はたして彼は捕まるだろうか」というサスペンスを感じることになる。このような語り口の名手として知られていたのが、アルフレッド・ヒッチコックである。しかし、やや遅れて、老刑事と若い刑事というお決まりの刑事コンビが登場し、この2人の取り調べによって、もともと良心の呵責に苛まれていた若い男はあっさりと自白し、逮捕され、このサスペンスのパートは行き場を失ってしまう。
次に浮かび上がってくるのはミステリーのパートである。ここで被害者の父親が登場し、ここから先、カメラは主にこの父親を追う。父親は、娘の所持品から消えた携帯が気にかかる。さらに、なぜあの時、なんのためにあの場所にいたのかということも釈然としない。しかし、警察にとっては犯人はすでに逮捕されており、これ以上捜査の必要性は見いだせない。そこで、納得がいかない父親は独自の捜査を開始する。この父親を水谷豊が演じるのだが、普段よりもかなり抑制の効いた演技であり、老刑事役の岸部一徳が醸し出す脱力した雰囲気との相性もいい。
そして、父親の捜査は意外な事実を暴き出す。もっとも、クライムストーリーで後半に“意外な真実”が浮かび上がるというのは意外でもなんでもないのだが、ここでまた本作は、さらに語り口を変えて、最後のパートに突き進むのである。
整理しよう。第一部は、罪を犯した若い男が追い詰められていくサスペンスのパート、続いて、父親が娘の真の姿を知ろうとして、いったんピリオドが打たれた捜査を勝手に継続するミステリーのパート、そしてその“捜査”が“意外な真実”を明らかにしたとき、本作はようやく真のテーマを浮かび上がらせ、次のパートへと進んでいくのである。本作のテーマとは何か?それは人間関係というかけがえのない財産についてである。
私たちは日々のニュースによって、その日まで善良で立派な人間として生きてきた者が、交通事故を起こして殺人者に転落するという事件を見聞きしている。事故は、直接の被害者だけでなく、さまざまな人間関係に亀裂を入れ、間接的な被害者を多く生む。これまで培ってきたかけがえのない人間関係を徹底的に崩壊させてしまうことさえある。しかし、このようなことはいわば常識である。このような常識を語っているだけにとどまっているとしたら、それは私たちにたいした感動を与えないだろう。
ここで後半部分に観客に示される“意外な真実”に注目したい。ネタバレとならないように詳細は避けるが、この“意外な真実”はかけがえのないと信じていた人間関係が実は危ういものだったということを明らかにする。前半では、加害者と、助手席に同乗していた友人の関係がほとんど同性愛的とさえ思えるほどに仲睦まじく描かれていたのだが、2人の間には、『太陽がいっぱい』(60)のような屈折した思いがわだかまっていたことが明らかにされるわけである。
そして、本作はさらにもう一歩先へと進もうとする。痛ましい事件は起きた、取り返しのつかないことは起きてしまった。いくら新たな真実が明るみに出ても、それによって善良な若い男が人を殺してしまったことが覆るわけではない。父親にしても、彼と娘は引き裂かれたままだ。しかし、この事件によって出会い、新たに結ばれる人間関係もある。老刑事が父親を飲みに誘い、被害者の母親と加害者の妻がテラスで語り合う。不幸によって培われる人間関係が貧しいものだとどうして言えるだろう。サスペンスからミステリーへと語り口を変えつつ、水谷豊が最後に謳い上げるのは、生きることの奇妙さである。その奇妙さこそを愛そう、という生きる姿勢なのだ。
キャラクターの造形は実にステレオタイプである。血気盛んな若い刑事と清濁併せ呑んだような老刑事、さらに大会社の取締役の令嬢、嫉妬するライバルたち…。しかし、事件とテーマの語り口はかなりアクロバチックだ。果敢に挑戦し、人と人との交わりの大切さを描くことに成功した水谷豊は、本作で映画作家になったと言えるだろう。
文/榎本 憲男