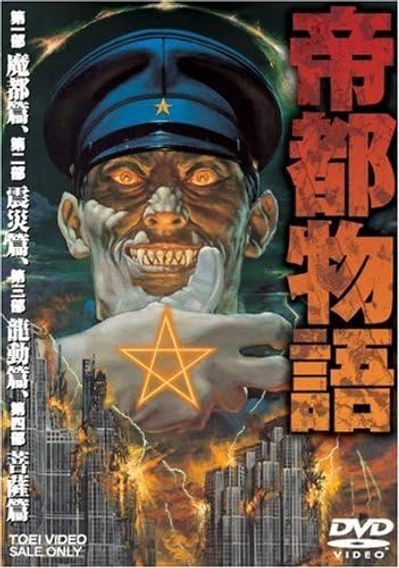『シン・ウルトラマン』イヤー開幕!樋口真嗣が語る、庵野秀明とのタッグと「ウルトラマン」と歩んだ道のり
『シン・ゴジラ』(16)に続き、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』(21)の庵野秀明と、「平成ガメラ」シリーズや『日本沈没』(06)の樋口真嗣という最強タッグが再度実現した空想特撮映画『シン・ウルトラマン』が、いよいよ本年5月13日(金)に公開される。メガホンを託された樋口監督は、いまどんな想いで本作に臨んでいるのか。鋭意製作中である樋口監督を直撃し、「ウルトラマン」との出会いからこれまでの道のりをたどると共に、『シン・ウルトラマン』への想いや情熱をめいっぱい語ってもらった新春特別インタビューをお届けする。
『シン・ウルトラマン』のキャッチコピーは「そんなに人間が好きになったのか、ウルトラマン。」。特報では、もうもうと煙立つなかで、成田亨がデザインした初代を彷彿させるウルトラマンがスペシウム光線を放っている。どうやら本作は、世界に誇る「ウルトラマン」というコンテンツを手掛けた先人たちへのリスペクトが込められた作品となりそうで、その強いこだわりの“原点”についても深堀りしていく。
「庵野から『初代ウルトラマンの世界観は、樋口向きなんじゃないか』と言われたことが始まりです」
――まずは『シン・ウルトラマン』の企画の成り立ちから聞かせください。
「『シン・ゴジラ』が終わって間もないころでしたが、庵野からまた一緒に映画をやらないか?という話をもらいました。おそらく庵野は、尻尾が生えたキャラクターよりも、人間形のキャラクターのほうに強く愛情を抱いてきたタイプなんです。そのなかでもウルトラマンは、自主映画時代に自分で演じたほどですから、ことのほか好きだったのではないかと。そんなウルトラマンを監督するのが、俺でいいの!?とも正直思ったのですが、庵野から『初代ウルトラマンの世界観は、樋口向きなんじゃないか』と言われたのが始まりです」
――確かに庵野さんは、自身がウルトラマンに扮した自主製作映画『DAICON FILM版 帰ってきたウルトラマン』(83)を監督されていますね。ちなみに樋口監督に向いているという初代ウルトラマンならではの世界観とはどういうものですか。
「初代『ウルトラマン』のドラマはとてもポジティブなビジョンの上に成り立っています。様々な怪獣や宇宙人が出てくるけれど、ウルトラマンや登場人物1人1人も含めて悲観的でない世界観がつむがれていたんです。そこが僕に合っていると思ったようです」
――それは『ウルトラマン』が放送された1966年~67年という時代背景とも関係しているのでしょうか。
「そうですね。1964年の東京オリンピック後で、高度経済成長も続いていてどんどん日本が豊かになっていくという期待感がありました。1970年に大阪での万国博覧会が開かれることもすでに発表されていたので、『ウルトラマン』にも古代怪獣ゴモラが万博に出現するというエピソード(第26話、27話「怪獣殿下」)がありました。まだ人類が月に行く前でしたが、きっと数年の間に行けると、なんの疑問もなく思っていただろうし、そういう明るい未来が待っていることを子どもたちに伝えようとしていたんだと思います。
科学は使い方を誤ればいろんな悲劇が待っているけれど、正しく使えばいいのだと肯定する立場に立って物語が展開されました。陽性の登場人物が物語の中心にいて、科学に対して疑問を呈するという展開になったとしても、そういう陰の部分はウルトラマンにおいては反定立だった。そのコントラストも含めて、あの時代にしか作れなかったすばらしい作品だと思います」
――『ウルトラマン』には、企画の中心となった金城哲夫さんをはじめ、上原正三さん、佐々木守さんらが脚本を、円谷一監督、飯島敏宏監督、実相寺昭雄監督らが演出を手掛けるなど、後世に残る様々なクリエイターが携わっていますね。
「例えば、のちに実相寺監督と佐々木守さんが手掛けられた『シルバー仮面』は第1話から変化球で、アウトコースすぎて多くの人には観てもらえなかったのですが、『ウルトラマン』のエピソードは、金城さんや円谷監督のように直球勝負を仕掛ける話があったうえで、実相寺監督や佐々木守さんがカウンターパンチを打つような幅の広さがあり、間口が広かったです。守るべき約束さえ守れば、あとはなにをしてもいいという、円谷英二監督の懐の深さが前提にあり、そういった幅に対応できるキャラクターの自由闊達な描かれ方も良かったです。自分が作る側になった時に、改めて『ウルトラマン』を見返してみると、本当にきちんと作られているなと感じます」