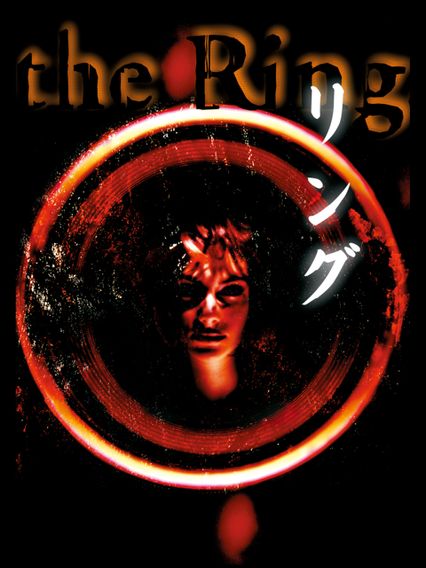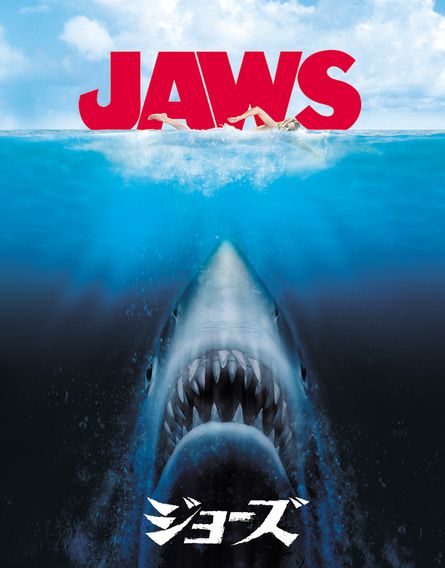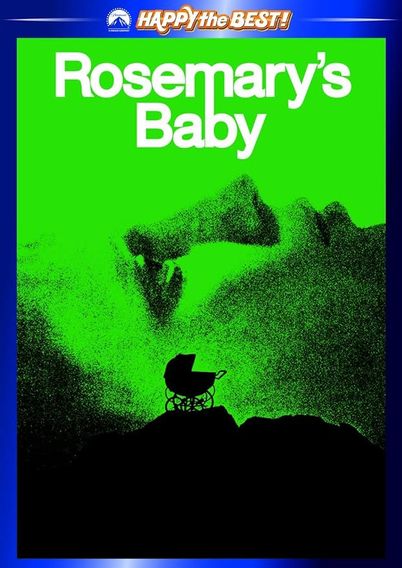黒沢清が夢見るJホラーの理想は「怖さと美しさの両立」ホラー映画の“美学”をふたつの観点から徹底的に語り合う!
第2部の「世界に伝播するジャパニーズホラーの美学」では、『回路』(01)をはじめとしたJホラー作品を手掛けてきた黒沢清監督と、映画監督で立教大学現代心理学部映像身体学科教授の篠崎誠の2名が登壇。1990年代に一世を風靡したJホラーが誕生するまでの日本の恐怖映画の歴史が辿られていく。
「Jホラーは、『リング』の貞子のように得体の知れないものがぬっと出てくる。サメがガブっと人を食べるのとはだいぶ違う類の映画」と説明した黒沢監督は、このシンポジウムの前にトークショーを行なったという共催企画「長谷川和彦とディレクターズ・カンパニー」で上映の自作『地獄の警備員』(92)を引き合いに出し、「あれは厳密にいえばシリアルキラーの話ですから、いわゆるホラー映画とは違います。その辺りの区別は非常に曖昧で、難しいものです」。
そして2人は戦後の日本映画界で多く作られていた“怪談映画”が、欧米的な“ホラー映画”へと転換した時期として「1977年」という具体的な年号を提示する。「アメリカ映画の影響が見られ、ホラー映画への一歩が見られた作品」と黒沢監督が挙げたのは伊藤俊也監督の『犬神の悪霊』(77) 。また大林宣彦監督の『HOUSE ハウス』(77)や野村芳太郎監督の『八つ墓村』(77)、洋画でも『キャリー』(76)や『家』(76)、『オードリー・ローズ』(77)などが相次いでこの年に公開されたという。
そこから1980年代の黒沢監督の活動を辿りながら、Jホラーの原点となったといわれる『邪願霊』(88)や、鶴田法男監督が手掛けた「ほんとにあった怖い話」シリーズの話題に。「これを観た時はとても衝撃を受けました。その頃まで塩田明彦や万田邦敏、青山真治らで集まって雑談しながら、なにが襲ってきたら怖いのかという話をしていましたが、『ほんとにあった怖い話』の『霊のうごめく家』は襲ってこない。ジャック・クレイトンの『回転』を日本のアパートでやれるとはまったく考えてなかった。ここから怖い映画への考え方を変えなきゃと思いました」と黒沢監督は驚きを込めて振り返る。
そんななかトークに加わったのは、数多くのジャンル映画を紹介するスペインのサン・セバスティアン国際映画祭のディレクター・ジェネラルであるホセ=ルイス・レボルディノス。海外でのJホラーの受け入れられ方について「ブームを巻き起こしたのは、もちろん中田秀夫監督の『リング』でした」と説明し、「私はその前から塚本晋也監督にも注目していました。小林正樹監督の『怪談』や溝口健二監督の『雨月物語』もありましたが、いわゆる日本のホラー映画に最初に注目するきっかけになったのは『鉄男』でした」と日本映画への愛を語る。
「『呪怨』や『リング』の後、長い髪の幽霊や顔の白い子どもがたくさん出てくるようになりますが、いまだに怖いと感じてしまいます。そうしたあからさまなもの以外にも、日本映画や日本文学の影響を西洋でもみられるようになりました。いまスペインではたくさんホラー映画が撮られている。そのなかに明らかにJホラーの影響があります」と語るレボルディノスに、黒沢監督は「日本ではブームがあっという間に去ってしまったJホラーが、いまだに続いているのは感慨深いですね」としみじみ。
そしてこのシンポジウムの最大のテーマである“美”について黒沢監督は、「元々ヨーロッパの怪奇映画が好きだったこともあって、それを日本でどうやるのだろうかと試行錯誤して悩んでいた時に、憧れていた美しさを封印したJホラーが現れました。怖さと美しさは相反してしまう。ただどこかで一緒になれるかもしれないという望みは捨てていません。いつかそれを両立させたいということが夢でもあり、今後このジャンルの映画が目指すべき一つの目標です」と、Jホラーのさらなる進化に期待を寄せた。
取材・文/久保田 和馬