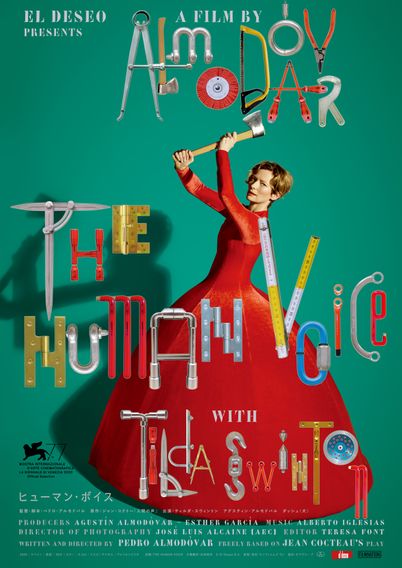フェミニストTシャツ、バレンシアガのセットアップ…『パラレル・マザーズ』『ヒューマン・ボイス』のファッションが優美に物語る“自由”
「戦友」という言葉がある。生きるか死ぬかの状況や、比喩的にそのような“戦場”を共に過ごすなかで生まれた友情のことを指す。女性にとって、子をこの世に産み落とすというのは、まさに生死と隣り合わせのことだ。“母”の物語をライフワークとして描いてきたペドロ・アルモドバル監督の最新作『パラレル・マザーズ』(11月3日公開)では、産科病棟で隣になり出会ったジャニス(ペネロペ・クルス)とアナ(ミレナ・スミット)が、まさしく「戦友」と呼べる絆でつながる。この2人の女性は、年齢こそ違うもののシングルマザーとして出産を決意し、同じ日に女児をこの世に誕生させたからだ。2人の人生は、それぞれのものとしてそれぞれの方向へ進む、はずだった。運命のボタンはかけ違ったのかと思いきや、実は同じループでつながっているのだった。
アーヴィング・ペンのポートレートに注目。インテリアがキャラクターを雄弁に語る
ジャニスは、シングルマザーとしてナニー(住み込みのベビーシッター)を雇いながら仕事もできる、あるいはしばらく仕事から離れても平気な蓄えのある、独立した女性。妊娠は予定外のタイミングでもあったのだろうが、年齢的には“今回産まない選択をしたら、子どもを持たない人生を選ぶことにおそらくなる”という年ごろだろう。これまでの人生を捧げてきた彼女の職業は、ファッション・フォトグラファー。
「写真の仕事ならなんでもするから!」と言って彼女がこなすプロジェクトは、スティルライフ(静物)なのだが、ルイ・ヴィトンなどラグジュアリーブランドのアイテムや、親友でもある上司のオフィスには、メディア露出を待ち構えるコレクションが並んでいるのがみてとれる。ただ、フリーランスとして生きる彼女のビジネスにおける“単価”を気にしないのであれば、彼女が一番情熱を傾けられるのは、ポートレートフォトなのではないだろうか。
母親を早くに亡くして祖母に育てられた彼女がライフワークとするのが、スペイン内戦に関連していると思われる彼女の地元や祖先にまつわることで、彼女の部屋のインテリアを見ればファミリーヒストリーを心底、尊敬していることは一目瞭然だ。彼女のダイニングには、アーヴィング・ペンのポートレートが飾られている。
「VOGUE」誌などで活躍し、グレーや白などのシンプルな背景が、そのモデルや被写体の個性を浮き彫りにするといった手法を生みだして、ファッションフォトグラフィーの礎を築いたと言われるペンの作品の中でも、「Nubile Young Beauty Of Diamaré, Cameroon」というカメルーンの民族たちを写した肖像写真を選ぶあたりが、実にジャニスがどのような女性であるかを雄弁に語っている。彼女は、人間を通じて、カルチャーや歴史を写真におさめることに興味があるのだ。
その写真を中央にはさみ、ダイニングテーブルで食事をしながらジャニスが向き合うのが、未成年だけれど母になることを決めたアナ。両親、特に母親の愛情を充分に得ることができなかった幼少期を過ごしたアナは、自らが“母”になることで、家族と向き合うことにする。アナが悲しい事実に直面し、途方に暮れそうになった時、不思議な縁によって再び引き合ったのが戦友、ジャニスだった。自立した女性の先輩でもあるジャニスは、お互いのためになるとサポートし合う生活を提案する。新しく始まる家族のスタイルを話し合う、そんな2人を見守るのが、先述のポートレートなのだ。
その人がその人なりの人生を生きたことを表す、服やファッション
そして、その時のジャニスが身に着けているのが、ディオールのコレクションから発表された「WE SHOULD ALL BE FEMINISTS(男も女もみんなフェミニストでなきゃ)」とスローガンが書かれたTシャツと「30モンテーニュコレクション」のコーディネイト。これは、2016年より同ブランドのクリエイティブディレクターに就任したデザイナー、マリア・グラツィア・キウリによるもの。
キウリは、1946年創立という長い歴史の中で、そのポジションに抜擢された初めての女性だ。パリの8区、モンテーニュ大通りの30番地には、ディオールの本社があり、アイコニックなアイテム誕生やその栄華をずっと見てきた場所。歴史あるメゾンの魅力をモダンに再解釈するコレクションにこの名を与え、女性の在り方の表現にこだわり、実用的ながらもロマンティックなエッセンスをデザインに取り入れることに定評のあるキウリのファッションは、このシーンをもっともエレガントに演出している。ほかにも秋冬2021-2022コレクションからキャラメルスエードのボンバージャケットや、メリノシープスキンのテディベアジャケットが採用されるなど、劇中にはディオールのアイテムが複数登場する。
その後、2人の数奇な運命の輪は、予想もしていない方向、ジャニスにとっては恐れていた方向へと大きく舵を切っていく。残酷なほどの真実は、かかわるすべての人物のベールをはがしていき、醜さ、弱さ、ずるさを丸裸にしていく。そういうふうに、なにも“着飾る”もののない素の自分だけが残った時、人というのは否応なしにルーツに立ち戻ったりするものだ。自分はどこから来て、そしてどこへ行きたいのか。プライドなんかをかなぐり捨てた時、本当に欲しいもの、必要なものはなんなのか。大小あれど、こういった想いは、世界中の人が体験したパンデミックを経て、多くの人に心当たりがあるのではなかろうか。
見苦しい姿も含めた自分と向き合うには痛みも伴うけれど、ジャニスの祖先の戦友たちに永遠の平和を届ける任務を経て、“家族”は再び集う。土に還った時、人はみな等しく骨だけになるかもしれないが、その人がその人なりの人生を生きたことを、身に着けたものが語る。人が社会を形成して生きる人間たる所以なのは、服やファッションが単なる布ではないという証明だ。その人のルーツやステートメントをなによりも優美に物語ることがあるのだ。