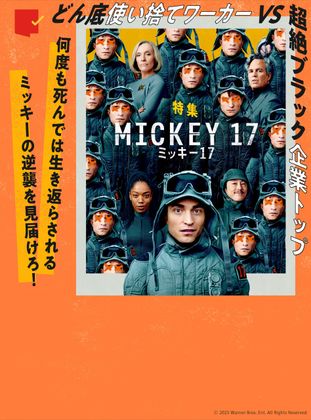稀有な役柄に命を吹き込んだ、『ある男』 窪田正孝の新たなる芝居を目撃する
「愛したはずの夫は、まったくの別人でした――」。芥川賞作家・平野啓一郎の同名ベストセラー小説を映画化した『ある男』(公開中)で、窪田正孝は俳優があまり巡り合うことのない稀有な役柄に命を吹き込んでいる。なにしろ、彼が体現したのは事故で亡くなった後に、映画のキャッチにもなっている、冒頭に書いた衝撃の事実を暴かれる謎の男「X」。つまり、どこで生まれ、どんな生き方をしてきたのかまるで分らない、幽霊のような男にまんまとなりきっているのだ。
しかし、よくよく考えてみると、人は誰でもなにかを演じて生きているし、状況やシーン、対峙する相手によって佇まいや見せ方を変えたりする。なかでも俳優を生業にしている人たちは、映画やドラマ、舞台などの劇中では与えられた役を生き、必要ならば料理人やピアニストとしての腕も磨くし、ボクサーなどを演じる際には肉体改造も率先して行う。逆にその俳優自体の素顔を知る人は本人や家族以外は知らない場合がほとんどだから、映画やドラマで役を生きる俳優の仕事は、何かのために素性を隠し、「大祐」という男として生きる「X」の行為とそんなに変わらないことなのかもしれない。
窪田正孝はいまでは誰もが知る、若手の実力派俳優のひとりだ。2020年前期のNHK連続テレビ小説「エール」で作曲家の古関裕而を演じ、将来が有望な若手俳優に送られるエランドール賞新人賞を受賞。映画でも多彩な役に“その人にしか見えない”自然体で挑んでいる。
映画『ある男』の石川慶監督は「『ふがいない僕は空を見た』(12)の窪田さんの演技が強烈に頭に残っていて。狂気を孕んだ危うさみたいなものをやらせたら抜群だなあ」と公式インタビューで評しているが、確かにあの映画の彼は鬱屈した感情を抱えた主人公の高校生・卓巳(永山絢斗)の親友・良太そのものだった。
良太は男のもとへ走った母親の代わりに、団地で認知症の祖母の介護をしながら暮らし、コンビニや新聞配達のバイトでギリギリの生活をしのいでいる。それでいて他人の施しを受けるのを嫌い、どこかですべてを諦めている。窪田はそんなどこにもぶつけられない良太の怒りや悲しみの負の感情を、セリフではなく、表情や瞳の繊細な変化、肉体から滲み出る狂おしい空気などでリアルに体現。表向きはあるトラブルで窮地に追い込まれた卓巳を心配する態度を見せながら、裏では彼を貶める行為を嬉々とした表情で続ける良太の歪んだ感情を生々しく伝え、観る者の心を大きく揺さぶった。
この良太役へのアプローチにこそ、窪田正孝という俳優の天性のスキルを感じる。彼はキャラクターを必要以上に作り込まない。嘘の芝居をしない。“自分”とかけ離れていない、自分の理解の範疇を超えないフィールドの中で演じるキャラクターをとらえ、必要な肉づけを行っているような気がしてならないのだ。
だから、窪田が演じる数々の役はパブリックイメージの彼の印象を残しながらもどこか違った人物に見える。しかし、そこに流れる感情は彼や私たちの中にも流れる嘘偽りのないものだから、多くの人たちの共感を呼ぶのだろう。