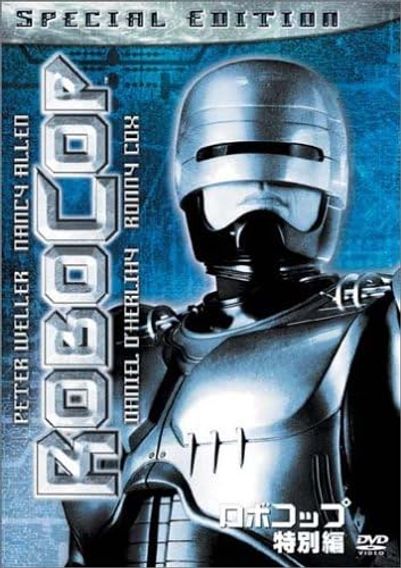ヴァーホーベンの感性に世界が追いついた!フェミニズム的視座でひも解く『ベネデッタ』への系譜
第74回(2021年)カンヌ国際映画祭での上映時、客席が騒然となったというレポートの文言は納得!本当におもしろすぎる。御年84歳の永遠の問題児、ポール・ヴァーホーベン監督(1938年生まれ)はまさに衰え知らず、むしろさらに調子が上がっているのではないか。
パワーが落ちない80代といえば、リドリー・スコット監督(1937年生まれ、85歳)がいるが、スコット監督は近作の『最後の決闘裁判』(21)で意識的かつ明確にフェミニズム色を打ち出した。対してヴァーホーベンの場合は、やっていること自体は昔から基本変わっていない。しかし時代のほうが追いついていった。フェミニズム的な視座からの「ヴァーホーベン読解」もどんどん肯定性が増していった印象がある。今回の『ベネデッタ』(公開中)も、ヴァーホーベン的な女性像をめぐる物語として非常に興味深い。
権力を手にする女性に惹かれ、描き続けてきたポール・ヴァーホーベン
主人公のモデルは17世紀のイタリアに実在した、伝説の修道女ベネデッタ・カルリーニ。修道院長の座に登り詰めつつ、同性愛者として裁判にもかけられた彼女の肖像は、J.C.ブラウン著「ルネサンス修道女物語―聖と性のミクロストリア」(ミネルヴァ書房刊)というノンフィクション本にまとまっている。
ヴァーホーベン監督は、ベネデッタという人物像に関して「手段はどうあれ、完全に男が支配する社会で、才能、幻視、狂言、嘘、創造性で登り詰め、本物の権力を手にした女性」と規定している。
それはヴァーホーベンのフィルモグラフィで暴れてきた魅惑的なヒロインたち――『氷の微笑』(92)で殺人事件の容疑者となるミステリ作家キャサリン(シャロン・ストーン)、『ショーガール』(95)の野心的なダンサーのノエミ(エリザベス・バークレイ)、『ブラックブック』(06)のナチス・ドイツ占領下をサヴァイブするユダヤ人女性エリス(カリス・ファン・ハウテン)、『エル ELLE』(16)で自分をレイプした犯人の男を支配するゲーム会社の社長ミシェル(イザベル・ユペール)の系譜に連なるもの。そう、すべて傑出した能力を持つパワータイプの女性だ。
ベネデッタ(『エル ELLE』にも出演したヴィルジニー・エフィラが快演)は既得権益の場を撹乱していくトリックスターである。幼い頃から神のヴィジョンを見たと言い張り、「私はキリストの花嫁」と自称して、修道院の権力を握るようになる。果たして彼女は嘘つきなのか、ある種の本物なのかはわからない。だがとりあえず、バルトロメア(ダフネ・パタキア)という父親や兄から性的虐待を受けていた女性を修道院に保護できたし、修道院のシステムを解体し、カトリック教会の男性優位や欺瞞を糾弾する形にも転がっていく。
つまり革命を起こすわけだ。あのジャンヌ・ダルクだって「本物」なのか「誇大妄想狂の少女」だったのかは誰にもわからない。ともあれ、世界を変革してしまう女性のパワーというものを、ヴァーホーベンは熱っぽく見つめているし、それに憧れ、強烈に惹かれているのは間違いない。