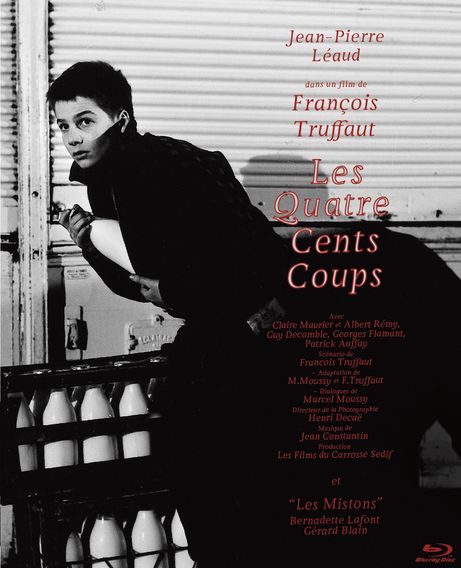『CLOSE/クロース』ルーカス・ドン監督が語る、“走る”ことと“視線”の意味「見過ごされたアザとこの映画でつながりたい」
主人公の少年の心の動きをあらわす、“視線”の使いかた
「『Girl/ガール』も『CLOSE/クロース』も、10代の主人公を描いた作品です」。ドン監督は、前作と今作の関係を「対になった作品として観ることもできるでしょう」と表現する。
「『Girl/ガール』は自身の肉体をコントロールしようとする映画でした。私たちの生きる世界では、生まれ持った体に紐づいた役割を押し付けられたり、それに紐づいているルールに沿って期待されたりして、答えを出さなくてはなりません。対して『CLOSE/クロース』もコントロールの映画ではあるけれど、こちらは振る舞いをコントロールすることについての映画です」と自ら分析を進めていく。
そのうえで重要なポイントとなるのは“視線”であり、両作でその使い方は明確に異なっているのだとドン監督は語る。「『Girl/ガール』では主人公のララが、自分の肉体をコントロールするとはどういうことなのかを意識する。それを描くうえで、常に身体が写っていることが重要でした。身体にフォーカスが置かれることで、そこに避けられないなにかがあるのだと観客も感じるようになる。そのために劇中では鏡が用いられました」。
一方で『CLOSE/クロース』においては、レオが大きな瞳で周囲を見る描写が頻繁に登場するが、なにが見えているのかほとんど明示されない。また『Girl/ガール』のように鏡を見ることもない。「レオは他の男の子たちを見て、彼らと同じように行動しようとします。彼は自分自身であることよりも、集団の一員でありたいと考えて行動するのです。なので、その視線が無意識によるものであることが重要でした。無意識でいられる世界から、少しずつ意識が入り込んでくることで、ようやく周りを見始める。そういう使い方を本作では取り入れています」。
それでも劇中では、鏡の代わりにレオがガラス越しにレミと向き合うショット、またレオがガラスに反射した自分自身と向き合うショットがそれぞれ登場する。前者は映画の比較的序盤、ホッケー場のシーン。「ここではレオがホッケーの防具をつけているため、レミでさえもレオのなかに入っていくことができないし見ることもできない。シールドが張られ、2人が分断させられているシーンといえるでしょう」と、ドン監督は説明する。
「ウォルト・ホイットマンの『We two boys together clinging』という詩にある『2人の少年が互いにすがりつき分かつことが難しい』という表現が、とても美しいと思っていました。男性同士でペアやバディを描く表現はあるけれど、彼らが切り離すことのできない者同士であるという表現はあまりされません。レオとレミの間にあるのは、制限もなく、名前をつける必要もない関係性の愛です。それはある意味、2人で1人の人間なのだと解釈できるかもしれません」。
そして、レオがガラスに反射する自分自身のぼんやりとした姿を見るシーンは終盤に登場する。「このシーンでは、どのようにレミの存在感を残すかが大きな挑戦でもありました。物理的に不在な人物をそこに存在させることができるのか。自分の分身だと思っていた人がいなくなったとき、人はどうするのか。それを自分なりに掘り下げたいという思いがありました。その答えは、このシーンと次の花畑のシーンとの組み合わせにあるのかもしれません。その二つのシーンによって、レオとレミの物語はあるべきところに着地するのです」。
取材・文/久保田 和馬