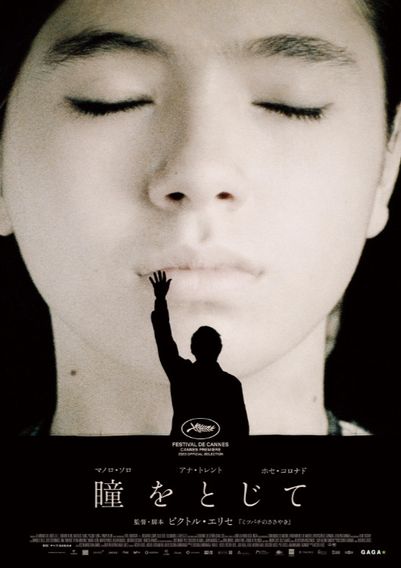スペインの巨匠、ビクトル・エリセ監督が31年ぶりの新作『瞳をとじて』に注ぐ魂の言葉とは
<ビクトル・エリセ監督のディレクターズノート>
「私はどんな映画を作りたいのか?そして、それはなぜか?
できるだけ短い言葉で正確に伝えるなら、答えはこうだ。
『私が書いた脚本から自然に花開いた、純粋で誠実な必然によって生まれる映画』
でも、この答えだけでは十分でないだろう。
だから『瞳をとじて』が必然として伴う“なにか”について説明したい。
そのためには概念の領域を掘り下げる必要があるが、私の意図を明確に宣言する。
もちろん、それはよき意図だ。
よき意図がよい結果を生むとは限らないと、わかっていたとしても。
プロットの細部を積み重ねた果てに、この映画が観客に向かって描こうとする物語は、
密接に関わる2つのテーマ“アイデンティティと記憶”を巡って展開する。
かつて俳優だった男と、映画監督だった男。友人である2人の記憶。
過ぎゆく時の中で、1人は完全に記憶を失い、
自分が誰なのか、誰であったのか、わからなくなる。
もう1人は、過去を忘れようと決める。
だが、どんなに逃れようとしても、過去とその痛みは追ってくることに気づく。
記憶は、テレビの映像としても保存される。
人間の経験を身近な形で記録したいという現代の衝動を、
なによりも象徴しているメディアだ。
映画を撮る者の記憶は、ブリキ缶の棺に大切に保管されたフィルムだ。
映画館のスクリーンから遠く離れて、
映像視聴メディアによって社会における居場所を奪われた、
それぞれの物語の亡霊たち。
この文章を綴る者の記憶と同じように、長く刻まれる。
これらの特性を内包した物語は、半分は経験したこと、半分は想像から生まれた。
私は映画の脚本を、自分で書いている。
だから、私が人生において最も関心を抱いていることが、
作品のテーマだと考えるのは自然なことだ。
言葉では伝えきれないが、1本の映画を観た経験が主役となる
詩的な芸術性に属するものだ。
そういう意味で、『瞳をとじて』では映画の2つのスタイルが交錯する。
1つは舞台と人物において幻想を創り出す手法による、クラシックなスタイル。
もう1つは現実によって満たされた、現代的なスタイルである。
別の言い方をするなら、2つのタイプの物語が存在する。
一方は、伝説がシェルターから現れて、
そうだった人生でなく、そうあるはずだった人生を描く物語。
そしてもう一方は、記憶も未来も不確かな世界でさまよいながら、
いままさに起こっている物語だ」
文/山崎伸子