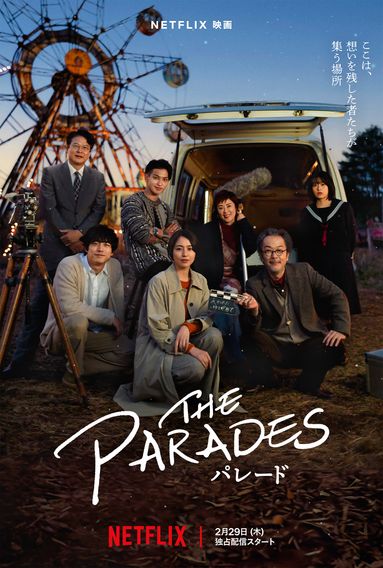長澤まさみ&リリー・フランキー「同志であり、もはや家族のよう」語り合ったお互いへの信頼感と死生観
「その時ごとに、自分のベストを尽くして生きていく」(長澤)
――マイケルは、美奈子に励まされながら映画づくりに奔走していきます。美奈子がマイケルの手をそっと包み込むシーンもとても印象的でしたが、信頼し合うお二人が演じたからこそ、すばらしい空気感が生まれていたように感じます。率直な疑問として、お二人はなぜこんなにも仲がいいのでしょう。
リリー「ただ、馬が合う。人生においてそういった友だちがいることって、とても豊かなことだなと思います。なかなか女友だちなんてできないのが当然というなかで、そういう友だちができた。まあちゃんには、男友だちと一緒にいるような感覚で『買い物、付き合って』とか言えますからね」
長澤「先ほどもお買い物に行く約束をしました(笑)」
リリー「春物を買わなきゃねって。そしてこの人ね、僕のことを“おばさん”だと思っている傾向がある(笑)。服をくれる時も、ちょっとサイズ感が小さ目なものだったりする」
長澤「あはは!そうですね。“リリーちゃん”って呼んでいます」
リリー「今日はハンカチをもらいました」
長澤「インド土産のハンカチ(笑)。お互いにかわいいものが好きなので、かわいいものをプレゼントし合っています」
リリー「まあちゃんは突然電話してきて、『最近、どうしている?』『元気?』『いま大丈夫ですか?』という取っ掛かりなしに本題に入るんですよ。突然電話をしてくる人なんて、僕にとってまあちゃんとミッツ・マングローブくらいしかいない(笑)」
長澤「俳優として尊敬しているからこそ交友関係を続けたいという想いもありますが、単純に一緒においしいものを食べたり、楽しいものを見たりしているだけで、気が合うなと。いつまでもやり取りをしたい人だし、“人生のなかにいる人”というか、もはや家族みたいな感じです。そういった出会いはなかなかあるものではないので、ありがたいし、不思議だなと思っています」
――旅立ってしまった人と、遺された人。それぞれがお互いの幸せを願っている姿を映しだす本作は、一度きりの人生において大切だと思える人と出会えることの尊さを噛み締めたり、旅立ってしまった人に想いを馳せることのできる映画です。お二人が本作を通して受け取ったのは、どのようなことでしょうか。
長澤「本作を通して『もし自分があと何日かしか生きられないとなったら…』と考えた時に、『まだ死ぬのは嫌だな』という気持ちが湧いてきて、自分でも少し驚いたんです。どことなくだけれど、そういう時が来てしまったら仕方のないことだし、受け入れるしかないだろうと思ったりしていた。でもそこに向かっていく自分を想像したら、まだやり残したことはあるだろうし、生きることを頑張りたいという気持ちが強いんだと気づいて。私は、『生きたい』という想いが強いタイプだったんだなと思いました。そういった意味でも、映画を通して自分自身と向き合ったり、生きることについて考えたりすることがあるんだなと改めて感じています。なかなかきっかけがないと、そういったことに向き合う機会ってなかったりしますよね。それは一生懸命に生きている証拠でもあるし、その時ごとに自分のベストを尽くしていくしかないなとも感じています」
リリー「ここ何年か、周りの人が亡くなることが多くなって。これが歳を取るということなんでしょうね。もし100歳まで生きたとしたら、ほとんどの人と死に別れなくてはいけなくなってしまう。それは相当、タフな人生になるでしょう。劇中で(横浜)流星が演じる勝利が、恋人に会いにいくシーンがありますよね。僕はあそこを観ていて、ちょっと泣けてしまって。生きている人は次に進んでいかなければいけないし、人間はそうやって頻繁に別れを繰り返していくものなんだなと感じています。『海街diary』という映画をやった時に、是枝(裕和)監督が『生きることと死ぬこと、両方を描く必要がある』と話していました。あの映画では、お葬式のシーンがあったかと思うと、四姉妹たちがご飯を食べていたりと、生と死が一緒に描かれますよね。この映画も同じような側面があって、生と死に向き合っている。とはいえ、生きること、死ぬこととはどのようなことだろうと考えてみても、考えれば考えるほどドツボにハマってしまうものでもあって。天国に行くためにはどうしたらいいか、なんて思ってみてもしょうがないですから」
――やっぱりお二人のように気の合う友だちを見つけたりしながら、必死に毎日を生きるしかない気がします。
リリー「そうなんですよね。だからこそ死者を身近に感じたりしながら、まあちゃんが言ったように日々のことを一生懸命にやって、たまに酒を飲んで後悔のひとつもする…というぐらいの生き方がいいのかなと思っています」
取材・文/成田おり枝