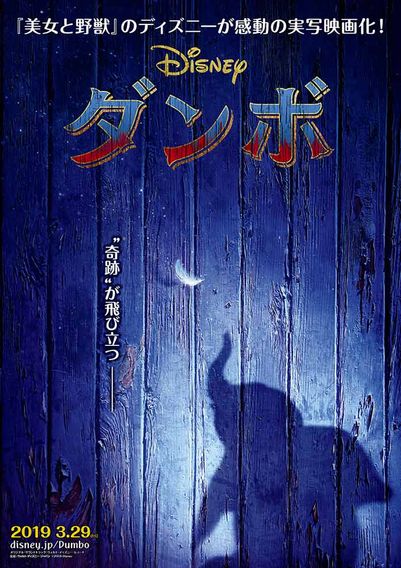竹内まりやが語る、拒絶できない“生”を歌い続けた40年、作品に託したささやかな希望
「英語で表現したくなるのは、『自分のスタイルってことにしちゃおうかな』と開き直ってます(笑)」
竹内の作品を特徴づける要素の一つに、バイリンガルである彼女の感性を生かした日本語と英語がボーダレスな作詞世界というものがある。このことについて尋ねると、「本当は日本人なので日本語で歌いたいんですけれど、やっている音楽がポップスなので、洋楽的な様式の音楽づくりを続けていると、どうしても言いたいことが日本語で収まらない時があるんです」と告白。「例えば『マンハッタン・キス』の歌詞の最後、“Till I hear you say you love me Don't disturb.”なんていうのは、日本語で言ってしまうと重くなってしまうんですけど、英語で表現することによってすっきりとリズムに収まる表現になりますよね」。
「他の作曲家の楽曲でもそれは同じで、独身時代にリリースした『グッドバイ・ユニヴァーシティ』の場合は、最初に梅垣達志さんが書かれたメロディを聞いたときに『これはもう、英語じゃないと表現できないな』と考えて、全部英語詞にしたんです。『カムフラージュ』なんかにしても最後のワンフレーズは英語ですし、長年そうしてきた結果、『自分のスタイルってことにしちゃおうかな』と開き直って、恥ずかしげもなくやっています(笑)」。
「“生きること”は拒絶できない。だからこそ日々の一瞬一瞬を面白がって生きたい」
山下達郎は、先日NHK総合で放送された特別番組「竹内まりや Music&Life ~40年をめぐる旅~」のなかで、竹内の作品が長年リスナーに愛されている理由として「人間存在に対する強い肯定感が魅力である」と語っていた。それについて竹内は「ことさら意識して『ポジティヴな作品を書こう!』と思ったことはないのですが、結果として私自身の潜在的な想いが出てきているのかもしれません。彼がそう分析するならば、多分そうなのでしょう」とにこやかに述べ、「人間、生きていればいいことばかりじゃないのだということはみんなわかっているけど、『それでもなお、夢や希望は持っていたい』と常に考えるタイプの人間ですので、それが自ずと出てきているのかもしれませんね」と自己分析。
さらに「“生きること”って拒絶できないじゃないですか。生かされているわけですから、だったら日々の一瞬一瞬を味わいながら面白く生きたいと思っているんです。常に“面白がって生きる”、些末なことでもいいから、何かいつも素敵だなと思えることを探したり、誰かの良い部分に目を向けてみたりする。そういう考え方を、達郎は“人間存在に対する肯定”と言っているのかな」と語る。
竹内は、あえて渋谷の街中のカフェなど、人混みのなかで詞を書くことがあるという。彼女は「街を行き交うそれぞれの人たちが、何を考え何を感じているのか、すごく興味があるんです」と、その理由を明かす。「たとえばオフィスビルに蛍光灯の明かりが灯った窓がズラリと並んでいて、そこで残業している人が見えたりすると、『いま、あの人はどういう気持ちであそこにいて、何を考えているのかな』ということを想像したり。子どものころも、授業中に先生の話を聞きながら考えることは、『この先生は、授業が終わって家に帰ったら、奥さんとどんな会話をしているのかな』とか(笑)。それぞれの役割で“こうあらねばならない”みたいなことって沢山あるけど、その枷を外したときには、『あー、洗濯するの嫌だな』とか、皆そんなことを思っている…はずだよね!と、いつも考えてしまうんです」と、彼女の創作の根底にある他者への好奇心を吐露してくれた。
「ドラマの主題歌というオファーがあった際は、主人公が30代のOLだったら、30代のOLが普段何を考えているのか、どんなことに葛藤しているのかしら?と想像しながら書くんです。達郎はそれを『非常に作家的』だと言っています。こないだマツコ・デラックスさんと偶然お会いしておしゃべりしたんですが、『あなたの書いた「駅」なんて、しっとりした曲だけどわりとエグい女の歌よね。だってジーッと隣の車両から見てるんでしょ?』って仰って大笑いしたんですけど、当たってるかも(笑)」。
「自分の歌が会うことのない誰かに届いたり、人の心に寄り添っていったり。それが一番嬉しい」
そして竹内は、さらに深くクリエイティビティの内面へと迫っていく。「私は物語に“救いがない”というのが苦手なんです。どんな状況でもどこかに一筋の光を残しておきたい。例えそれが出口のない恋の歌だとしても、どこかに救いがあって、最終的にその主人公にとってプラスになってほしい。だからといって、なんでもハッピーエンドならいいわけじゃないけれど、ほんの少しでも希望がもてる部分を残しておきたい。『どこにも救いがない』という世界を描くのが役割の表現者もいると思うんですよ。そういう(ソリッドな)表現があってこそ、私みたいな“どこか能天気”な世界観が活きると思うんです」。
「達郎は“成就しない恋”を書くことが多いんですが、『あしおと』の歌詞みたいに、“きっと君の目には 僕は透き通ってる”というような表現の仕方が好きですね。それは彼のスタイルですし、そこには男性ならではのペシミズムやロマンチシズムがあると思います。その一方で、現実に対峙するにはどうしたらいいんだろうかと考えた時に、私はどこかに救いが欲しくなる。不倫を題材にしたドラマの『純愛ラプソディ』みたいな曲でも“優しさと強さを知ったわ”としておかないと、ただのドロドロでは救いがないですから(笑)。そのほうが、多分私の音楽性に合っているんだと思います」と、軽やかに話してくれた。
インタビューの最後に、竹内はこう総括する。「自分が意識しないところで、自分の放った言葉とかメロディが誰かの人生の役に立つって素敵なことだなと。これはこの職業をしていて、一番嬉しいです。自分の歌う歌が会うことのない誰かに届くとか、人の心に寄り添っていったりすることが音楽では起こる。作り手の想いが届いて、その歌を歌ってもらえたり、聴いてもらえたりするのは本当にありがたいことです。だからこそ40年、続けてこられたのかもしれないですね」。そう語る竹内の瞳は、新たな創作活動へと向かってゆく、清々しい決意に満ちていた。
取材・文/編集部