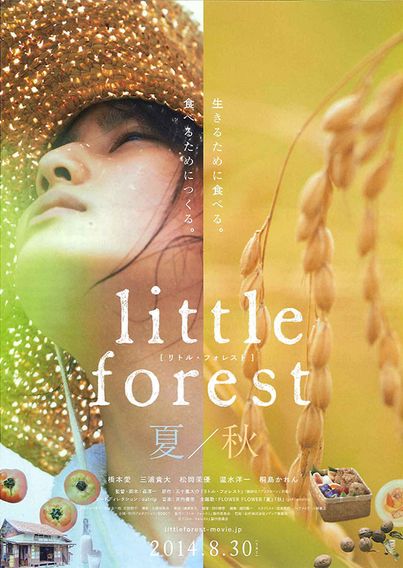橋本愛とキム・ボラ監督が語り合う、『はちどり』が描く死生観と“つながり”「人生をじっくりと覗き込んでいくことを表現したい」
「小さなことが大きな革命にもつながる」(キム・ボラ)
橋本「『はちどり』のなかですごく印象に残ったのが“つらいときに指を見る”ということ。指を見てなにを感じるのかなと考えたときに、いつもはつながっている体と心が乖離している。どうしようもなく心が重くても体は動くんだ、必死に動かしていけばいつか前を向けるかもしれないんだという希望をもらいました。
パンフレットのインタビューを読んだ際に、監督は心理学などに博識だと感じたのですが、あの言葉は監督自身の経験や思想から生まれたものなのでしょうか?」
キム・ボラ「そのセリフは、10年くらい前に知り合いのお姉さんから聞いた言葉だったんです。とても印象に残っていたので、彼女に許可をとって映画のセリフに使わせていただきました。人はつらいときに、大きな助言が必要な気になるものですが、実際には小さくても日常的な助言が力になることがあります。
私自身、『はちどり』を準備している時に憂鬱になることがありました。ベッドから起き上がるのもつらくて、一日を始めることがこんなにも苦しいのかと思えた時に、その言葉を思い出し、指を動かすという小さなことでもいかにそれが大きなことであるかと気付かされました。また一日をスタートできることが自分にとって大きなことだと感じられると、とてもうれしく思えました。
私は心理学にも関心がありますし、20代の頃からずっと瞑想をしてきました。瞑想では、息を観察して覗き込むことを教えられます。最初は難しく感じていたのですが、後になって実際にそれが役に立っていたと体験して実感するようになりました。小さなことが大きな革命にもつながる。是非映画のなかでセリフとして取り入れたいなと思ったんです」
「つながっていると知ることが、まさに生きていくこと」(キム・ボラ)
橋本「私自身は、身近な家族や友人、いつも向き合っている人たちを亡くしたことはないのですが、監督が先ほどおっしゃっていた『毎日人は死んで生まれてを繰り返す』という死生観は私にもあります。
映画の中で、最後の大きな出来事として橋の崩落が描かれていますが、ウニの日常には小さな橋の崩落のような出来事がいっぱい描かれていた。それらが積み重なって、成長していくのを見て、監督自身もあの出来事を経験して、それが死生観に影響を与えたのだと感じました。その当時どんなことを感じて、それがいまの監督自身にどのようにつながっていると思われますか?」
キム・ボラ「ソンス大橋の崩落事故は、韓国で生きているすべての人々に共通するトラウマとして記憶に残る事件だったと思っています。私自身、そこで身近な愛する人を亡くしたりはしませんでしたが、子供心にもうまく言葉にできない気持ちに襲われたことを覚えています。
その後事故のことを忘れて生きてきましたが、『はちどり』の準備をしている時に、真っ二つになった橋の写真を見ながら体の痛みを感じました。私たちは蓋をして生きているけど、身体の中には間違いなく残っているの。そして初稿を書いていた時に、セウォル号の事故が起きました。その時にデジャブのような気持ちになって、こういう事故が繰り返し起きているのだと感じました。
橋本さんのおっしゃった通り、この映画はウニの内面で起こる様々な小さな崩落が、社会の中で起こった大きな崩落とどのようにつながっていくのかを映画的に表現したいという気持ちがありました。韓国で公開された時に様々なコメントが寄せられたのですが、その中に『子どもの生まれた日にソンス大橋が崩落し、いまでも子どもの誕生日になると思い出す』という書き込みがあって、自分自身の身近なものとして体験しなくても、他人の涙や苦しみ、死が自分のことのように感じられたり、つながっていると知ることが、まさに生きていくことなのではないかと感じました。
当時、私は橋の近くに住んでいて、実際に家族や親しい友人を亡くしたわけではありませんが、自分の中でなにかを失ってしまったと強く感じていました。それは言い換えると、誰か他人と世界がつながっていることではないかと思います。『はちどり』を書いている時期に、身近な人を失うことを経験しました。
映画のなかで、叔父さんを亡くした母親にウニが『どんな気持ちだった?』と聞き『変な感じがする』と答えるシーンがありますが、私自身もその心境でした。身近な人がいなくなるのはとても不思議なこと。いつなにがあるのかわからないものだと思い、だからこそ自分が感じている愛する気持ちや、感情を思う存分表現して生きていきたいと思うようになりました。
喪失を通じて、人生を覗き込むようなきっかけになった。この映画では、人生をじっくりと覗き込んでいくことと、その経験を通じてどう生きるべきかを伝えて表現したいと思いました」