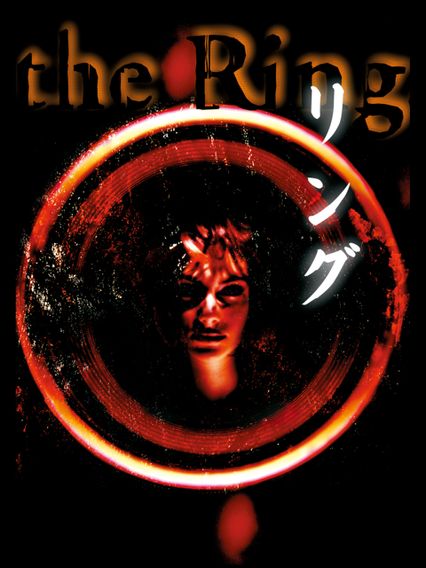「本物の幽霊が、ゲームに映りこんだ」清水崇×ホラーゲーム「零」開発者が語りあう、恐怖の生みだし方
この世のものとは思えないものを写す武器“射影機(しゃえいき)”で襲いかかってくる悪霊たちを撃退していく人気和風ホラーゲーム「零」シリーズの20周年記念作「零 ~濡鴉ノ巫女」が10月28日(木)に発売される。これを記念して、シリーズの生みの親である菊地啓介プロデューサーと柴田誠ディレクター、「呪怨」シリーズや『牛首村』(2022年公開)で知られ、現在応募受付中のフィルムコンペティション「日本ホラー映画大賞」では審査委員長を務めるJホラーの巨匠、清水崇監督のスペシャル対談が実現。「零 ~濡鴉ノ巫女」の話題を中心に、恐怖演出に対するこだわりから制作時の貴重なエピソード、背筋が凍るような実際の恐怖体験までを、ゾゾゾッと語り尽くしてくれた。
「霊を引きつけて撮らないといけない“射影機”のアイデアはすばらしい」(清水)
――「零~濡鴉ノ巫女~」のプロモーション映像をご覧になって、清水監督はこの作品の設定や世界観をどのように思われましたか?
清水「僕が普段やっている実写の映画でもそうなんですけど、ホラーとファンタジー、アクションはどうしてもないまぜになってきます。そこは問題ないのですが、あくまで最後まで怖さを狙っていたとしても、クライマックスの大団円的なところではどうしてもアクションに寄りがちで。そこをどうしたらいいのか、というところでいつも苦しんでいるんですよね。まあ、掘りだした骨を埋めて成仏させたり、お札を使って除霊したり、いろいろ手立てはあるんですけど、『零~濡鴉ノ巫女~』の“射影機(撮影することで怨霊を撃退し、封じ込める力を持つ古いカメラ)”という発想はすばらしいなと思いました。しかも、霊を引きつけて撮らないといけないというのがいい。少し前に『ポラロイド』というアメリカのホラー映画があって、それはポラロイドカメラで撮られた被写体の人物がが謎の死を遂げるというミステリー展開だったんですが、あの映画も、ラストは『その手しかないよね』と思わせる秀逸な結び方で、アクションにいき過ぎずに絶妙なバランスで怖さを残していました。『零~濡鴉ノ巫女~』はゲームなので、もっとインタラクティブな結末があるのでしょうけれど、情緒的な怖さを失わない“射影機”のアイデアは秀逸だと思いましたね」
菊地「ちょうど20年前に誕生した『零』シリーズのストーリーや世界観は柴田がすべて作っているんですけど、私たちも『カメラで霊を倒す』という設定を最初に聞いた時は“なんだ、そりゃ?”と思って(笑)。清水監督がいま言われたお札や破魔矢なんかじゃないと効き目や攻撃している感じが出ないような気もしたんですけれど、心霊写真とも親和性があるカメラをゲームのシステムに組み入れてしまったいまは、武器はもうこれしかないという感じになりました。カメラで写真を撮るという行為は、ゲームでいうところの銃撃に近いものですしね」
清水「そうですよね。しかも、このゲームにおける写真撮影は怖いものが迫ってきても目を逸らしたり、逃げたりしないで、それと対峙しなければいけない。怖がりな方には一番辛いことですけど、嫌でも前のめりになるしかない(笑)」
菊地「このゲームには“シャッターチャンス”という設定があって、襲ってきた悪霊が怖い顔をした時にフレームが光るんです。そのタイミングに合わせてシャッターを切ると一番ダメージを与えられるので、プレイヤーは恐怖に耐えながら頑張ってそこを狙うわけですね。ただ、怖いだけじゃないんです」
――柴田さんはこの“射影機”のアイデアをどこから発想されたんですか?
柴田「僕の実家が幽霊の通り道に面していて、子どものころ、夜中に家の前を幽霊たちが通るというすごい体験をしていたんです。ただ、その百鬼夜行を見ると連れていかれると思っていたので直視しないようにはしていたんですよ。でも、父親から壊れたカメラをもらった時に、カメラで写真を撮ったり、カメラのフレーム越しに覗いたりするなら見たことにならないんじゃないかという子どもなりのルールができて。その時に、幽霊に対抗できるのはカメラしかない!という思い込みが強くなったような気がします(笑)」
清水「あ~、なるほど!1枚フィルターがかかっていて、直接は見ていないということですね」
柴田「そうです、そうです。レンズを通して見れば大丈夫なので、これなら幽霊に対抗できるという感覚があったんです」