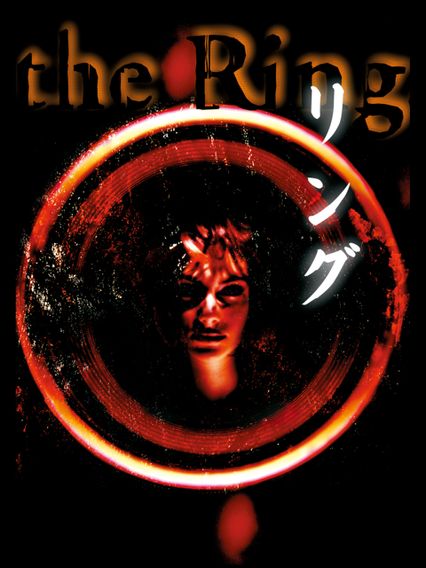「本物の幽霊が、ゲームに映りこんだ」清水崇×ホラーゲーム「零」開発者が語りあう、恐怖の生みだし方
「頭のなかに思い描いた恐怖を提供したい」(菊池)
――ここまでお話いただいた実際の怖い体験や不思議な現象をエンタテインメントに昇華させる際に、みなさんが大事にしているのはどんなことですか?
清水「雰囲気と気配ですね。学校や病院、トンネルでもそうですけど、廃墟になって人が寄りつかなくなった場所は、事故や事件が起きてなくても勝手に尾ひれがついて心霊スポット化しますよね。そこには人間が生みだしてしまう負のオーラのようなものがあるような気がしていて。自ら作りだしたものを放置してしまうと妙なうしろめたさが生じるし…投げだされた状況と痕跡に『なにがあったのか?』と過去を憂う妄想が働いてしまう。それは匿名で誰かを責めたり意見したりすることで、自分の居場所や精神を確立、安定させようとするネット社会にも通じるものがある。そのオーラや痕跡の存在感は人間の文化、所業が作りだすものですから、人類が滅びない限り絶対になくならないと思います」
菊地「『零』シリーズの開発の時も『なにが一番怖いんだろう?』という話になって、最終的に『想像力…人が想像するものが一番怖い』という結論に落ち着きました。見た目がグロいものより、頭のなかで思い描いたものの方が怖いから、想像力に訴えかける恐怖を提供しようという話になったんです」
柴田「尺が通常2時間前後と決まっている映画と違って、ゲームは自由に動いたり戻ったりできるので、そういう気配を感じる空間を作りやすいかもしれないですね。ただ『零』の空間は、怖いけれど、プレイしていくうちにすっと居心地がよくなってくるところがあって。懐かしい場所にいると感じたり、前にここに来たことがあるなって思ったりもする。ゲームというデジタルの世界でも、そういう雰囲気は出せるはずだという信念でやってきたところがあります」
「思い出してゾッとするような応募作品を心待ちしています!」(清水)
――今回、清水監督は日本初のホラー映画専門のコンペティション「日本ホラー映画大賞」(11月30日まで応募受付中)の審査委員長を務められているわけですが、この賞に挑戦しようと思っている次世代のクリエイターの方々に、清水監督流の怖がらせ方の秘訣やコツを教えていただけますか?
清水「よく訊かれますが、そこがわかったら苦労しませんし、おもしろくなくなってしまう気がしてます (笑)。その秘訣やコツの部分にこそ、個性や各人の幼少期からの感覚や生きてきた性分が垣間見えるとおもしろいんですよ。また、映画を作っていると、たまに自分の意図とは違う方向に行ってしまい、それでこそ生まれてしまう“魔の空気”みたいなものがあるんですよね。
例えば、トビー・フーパー監督の『悪魔のいけにえ』という名作がありますけど、フーパー監督に『あれと同じものをもう一度作れ!』と言っても、同じものはできない。あの頃、あのメンバーと監督の志向で、余ったフィルムを使うしかなかった環境下で、みんなで自主映画みたいなスタイルで作ったことで、ああいう仕上がりになったわけですから。ただ、そういう“魔の空気”を自分でコントロールできるようになったら凄いだろうなと思っています。いや、もうそうなったら“魔の空気”ではなくなってしまうのでしょうけど。
求めたいのはサプライズ(SURPRISE=驚き)ではなく、スケアリー(SCARY=恐ろしい。ゾッとする)。ずっと映っていたのに気づかなくて、ハッと気づいた瞬間にゾッとする…というところまで持っていけたら、上等だなと思っています。サプライズは比較的誰にでも編集や芝居のタイミングで作りやすいし、その場しのぎ感があるんですよ。ところが、スケアリーは狙いすますのが難しいし、監督やスタッフ、キャストの感性や撮影時の場の空気などが大きく影響する。出来のいいホラーは、家に帰ってお風呂に入った時や寝る直前に、思い出してゾッとしたりするものですよね。僕はそれを『お土産』って呼んでいるんですけど、本当に怖い作品には『お土産』が多い。そういう意味では、劇中の舞台も山とか神社、住宅地や普通の日本家屋など、生活を感じる日常からかけ離れすぎていない空間の方が適してくると思います」
――今回は3分の長さのショートフィルムから応募が可能で、アニメーションの部門も設けられているので、CG作品などでも怖い作品が集まってくれるといいですね。
菊地「そうですね。自分で作ってみるとまた違う怖さが感じられると思うので、『零』シリーズをいままで遊んでくれた人たちも、この機会に自分でショートフィルムを作って応募してみるのもいいと思います。そうすれば見識がさらに広がるし、楽しみも増える。そうやって、ホラーの裾野が広がっていくといいなと思います」
柴田「僕も自分でゲームを作ったからこそ不思議な体験ができたし、打席に立ってみないと神が降りてこないことって結構ある。なので、ホラー映画を作りたいと思っている人はとりあえず打席に立って、バットを振ってみる。そうすれば、きっと違う展開になってくるはずです。プランはもちろん必要ですが、打席に立つことでしか起こり得ないことはあると思います」
清水「僕の商業デビューのきっかけも、『呪怨』も、オリジナルは映画技術美学講座(現・映画美学校)の課題で提出した相当画質の悪いVHSの3分の作品ですから、今回の応募規定と似たショートフィルムだったと言えますね。『日本ホラー映画大賞』の企画者である小林剛プロデューサーともそんな話をして規定を設けましたし。画質や技術的な面などは拙くてもいいんです。僕のその課題作りの時は、編集機もなくて、家にある2台のVHSプレイヤーで細かなダビングを一人で繰り返しながらの編集でしたから、画質は最悪。ノイズの“虹”とかが出まくっている酷い見映えだったんです。やはり周囲の普通の人は『汚いな』『画質、悪っ!』止まりでした。でも、黒沢清さんや高橋洋さん、青山真治さん、塩田明彦さんら講師だった監督たちは、画質どうこうじゃなく中身の表現を褒めてくれた。それがキャリアの最初ですから、まずは打席に立って振ってみること。行動してみなければ始まらないのだと思います。僕も新たな才能に出会えることを、心待ちしています!」
取材・文/イソガイマサト