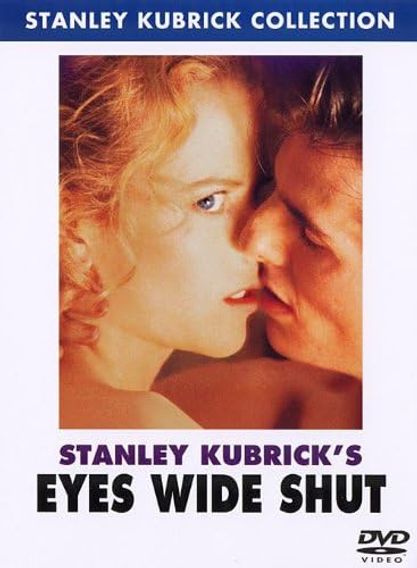衝撃作『TAR/ター』で奇跡の復活を遂げた“幻の名匠”トッド・フィールド、16年間の空白を語る【宇野維正の「映画のことは監督に訊け」】
インタビューの冒頭でそのままトッド・フィールド監督に伝えた「『TAR/ター』はこの10年間で作られたアメリカ映画の中で最も重要な作品の一つ」という言葉になんの誇張もない。数か月前に初めて『TAR/ター』を観た時の衝撃はまだ身体の芯にしっかり残っていて、それは今後も作品を観返すたびにフレッシュなものとして蘇ってくるだろう。前回のパク・チャヌク監督に続いて、結果的に2回連続で外国人監督へのインタビュー、それも今回は対面取材ではなくZoomでの取材というイレギュラーな形式となったが、取材相手がフィールドということでご容赦いただきたい。『イン・ザ・ベッドルーム』(01)で監督デビューして以来、22年でたった3本しか作品を残していないフィールドにインタビューができる貴重な機会をどうしても逃すわけにはいかなかったし、その内容をエディットせずに最もしっかり読者に届けられるのがこの連載だった。
インタビューでは、ネタバレを回避してまわりくどい質問をするような時間の使い方はせず、取材時間いっぱいに質問を詰め込んで、結果的に1万字を大幅に超える充実したものとなった。『TAR/ター』に関しては、日本語で読むことができるインタビューだけなく、海外のメディアによる監督インタビューも、主演のケイト・ブランシェットについて語っているパートが半分以上を占めるものがほとんどだった。世界中のアワードや映画祭で数々の主演女優賞を(当然のように)獲得した本作におけるブランシェットの貢献は、主演女優としてだけでなく、エグゼクティブ・プロデューサーとしても絶大なものであることに異論を挟む余地はまったくないが、監督の作家性を探ることを主旨とする連載ということもあって、このインタビューでは意識的に、海外を含む他の映画メディアの質問との重複を可能な限り避けた。
突出して優れた映画の多くがそうであるように、『TAR/ター』はネタバレによってその面白さや意義が損なわれるような作品ではないが、それでも気になる読者には作品を観てから本文を読み進めていただければと思う。いや、一度観たら必ずやもう一度観たくなるはずなので、初見とリピート鑑賞の間に読んでいただくのが今回のインタビューの内容をふまえると最適かもしれない。
すべての映画監督がそうであるべきとまでは言わないが、フィールドと会話をしながら強く感じたのは、PCの画面越しでも伝わってくる、映画批評家/映画ジャーナリストへの深い信頼と敬意だった。別に自分の質問がそうさせたと言いたいわけではない。批評への信頼や敬意がなければ、ハリウッドのメジャースタジオ作品として、『イン・ザ・ベッドルーム』、『リトル・チルドレン』(06)、そして『TAR/ター』のようなこれ以上ないほど大胆かつ繊細な映画を世に送り出すことなどできないだろう。
※本記事は、ストーリーの核心に触れる記述を含みます。未見の方はご注意ください。
「私たち映画人が生きてきたこの世界が終わってしまったような感覚が、脚本の全体、すべてのシーンに息づいているんです」(トッド・フィールド)
――『TAR/ター』はこの10年間で作られたアメリカ映画の中で最も重要な作品の一つだと思います。本国の公開から日本で公開されるまで時間差があったので、まずは、この作品がここまで多くの観客、そして多くの批評家に概ね大絶賛とともに受け入れられてきたこと、そして数々の賞を受賞したことについて、現在の率直な気持ちを教えてください。
「『インクレディブル!』の一言です。本当に、信じられないほど旺盛で、長期間に及ぶリアクションの大きさにとても驚いてます。『TAR/ター』が公開された後、その内容を巡っての議論が、アメリカでも、それ以外の地域でも、私たちが望んでいた通りのとても意義深いものとして広がっていきました。 アメリカでは2022年10月6日に公開されたのですが、先週(2023年4月中旬)になってもまだ新聞が社説で取り上げています。とりわけ批評家からの支持と評価という点では、ずっと夢に見ていたようなことが現実に起こったのです。監督としてだけでなく、作品に関わった全員にとって、そうした一連の出来事は最も喜ばしいことであり、心底興奮させられることです」
――映画には、観客によって多様な解釈を許容するタイプの作品があると思うのですが、『TAR/ター』は多様な解釈を許容する作品であるというだけなく、観るたびに新たな発見があって、作品の解釈や印象が揺れていくような作品だと思いました。これはまさに自分自身が体験したことなのですが、最初に観た時は異常に高揚した気持ちになって、2回目に観た時は数日間しばらく落ち込んでしまいました。
「なるほど(笑)。まずは、この映画がどのように生まれたかについてから話をする必要があるかもしれません」
――まだ製作が決まってない段階から、ケイト・ブランシェットが演じる主人公を念頭にしていたという話は聞いてます。
「2020年3月半ば、まさに世界中でロックダウンが始まった時、私は新しい脚本を書き始めようと意を決して自宅のデスクの前に座りました。あの時期は、もう自分は映画を作ることはできない、あるいは自分の作品だけでなく、この世界はもう新しい映画を求めてないのなかもしれない、そういうことを考えずにはいられない時期でした。だから、私は自分に手紙を書くように『TAR/ター』の脚本を書き始めました。その時点では、この脚本を映画として実現できるとは思っていませんでした。頭がおかしくなってしまわないために、なにかをやることが必要だったんです。まるで、世界が終わってしまったような感覚に陥ってました。きっと、それは私だけではないはずです。映画に関わってきた人間にとって、あの時期は頭がおかしくならないためになにかをすることが必要だったんです。だから、『TAR/ター』には私たち映画人が生きてきたこの世界が終わってしまったような感覚が、脚本の全体、すべてのシーンに息づいているんです」
――「自分に手紙を書くように」というのはどういうことですか?
「私はこの脚本を通して、すべてのシーンで自分自身に質問を投げかけているのです。それは、まるで自分の頭に銃口を向けるようなプロセスでした。だから、あなたの言うように、この作品の解釈には多くの可能性があります。まさにその解釈の可能性の一つ一つを、作品を撮り終えた後も私自身が共有してきました。モニカ・ヴィッリ(注:ミヒャエル・ハネケの諸作品で知られるオーストリア人の映画編集者)と私で作品を編集しながら、私たちは『今日はリディア(・ター)のことをどう思った?』と質問し合いましたが、私の答えも彼女の答えも毎日のように変わっていきました。あるいは、午前と午後でも――私たちは家族と離れてその作業をしていたのですが――その前に家族と電話でなにを話したかでも、それは変わっていくものなんです。映画というものは、生活と同じように、ほんの些細なことに影響されるものです。生活をしていれば、お腹が減っていて少し不機嫌になることもあれば、家族の誰かと口論して不機嫌になることもあります。家族の誰かに腹を立ててその場を立ち去るときでも、立ち去る瞬間に交わし合った一言で気持ちが和らぐこともあります。つまり、この映画はそのようにして作られているのです」
――本作を解釈する上で重要なシーンの一つは、リディアが若いチェリストのオルガを車で家に送った後、誰もいないアパートメントの中庭で起こる一連の出来事ですよね。一つの解釈として、あのシーン以降はリディアの頭の中の出来事、ある種の幻覚だと受け取ることも可能だと思います。それについて、このようなインタビューで言及すること、つまり作者の解説によって観客の解釈を固定させてしまうことに抵抗がありますか?まあ、おそらく抵抗があると思ってあえて訊いているのですが(苦笑)。
「OK(笑)。私はあらゆる映画が好きだし、観客が正確にどう感じるべきかを丁寧に教えてくれるような作品も嫌いじゃないです。ただ、私が最も好きなタイプの作品は、観客である私に最終発言権を与えてくれる作品です。つまり、あなたの質問に答えることは、もし私が観客だとしたら自分自身の期待を裏切ることになってしまいます。映画の解釈の権利はあくまでも観客にあると考えているので、もしその質問に答えてしまったら、どうやって自分の作品を人に勧めて、観てくれたことを感謝すればいいのかがわからなくなってしまうんですよ」