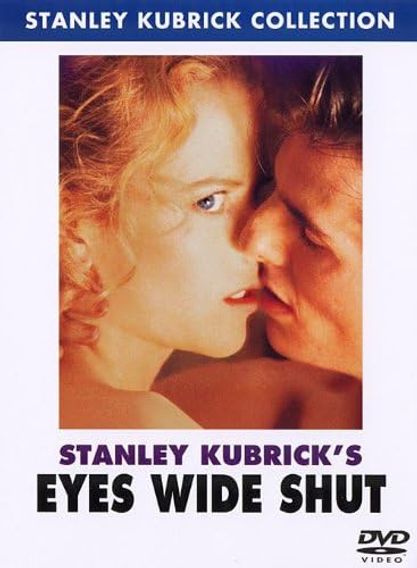衝撃作『TAR/ター』で奇跡の復活を遂げた“幻の名匠”トッド・フィールド、16年間の空白を語る【宇野維正の「映画のことは監督に訊け」】
「スタンリー・キューブリックは私を編集室に招き入れて、編集中の『アイズ ワイド シャット』のラッシュを毎日のように見せてくれました」(トッド・フィールド)
――あなたは映画監督になる前、役者としてウディ・アレンやスタンリー・キューブリックをはじめとする多くの監督たちと仕事をしてきました。彼らの作品の現場で体験したことは、あなたが映画を監督するようになった上でどのような影響をもたらしているのでしょう?
「役者の仕事に限らず、これまでの自分の人生で起こったことすべてが私の作品に影響をもたらしています。でも、そうですね…映画の世界に足を踏み入れてから40年近く経ちますが、映画監督という仕事をする人たちは、物事をとても効果的に、理にかなったやり方で、そこに参加している人たちに不安を持たせないように進めることができる、特殊な能力を持った人たちと言えるでしょうね。そういう意味では、一緒に仕事をする機会を得たすべての監督からたくさんのことを学んできました。私が最初に役者としてプロフェッショナルの現場に参加したのは、ウディ・アレンの『ラジオ・デイズ』でした。あの時はなによりもまず、彼の撮影現場にいることにとても興奮しました。なにしろ、あのウディ・アレンですからね。もちろん、私はそれまでの彼の作品をすべて観ていて、深く尊敬していました」
――撮影中に、あなたが映画監督になりたいと思っていることを監督に伝えるような機会はあったんですか?
「私が仕事をしてきた監督は、みんな私が監督になりたいと思っていたことを知っていました。なかでも私を強く後押ししてくれたのは、カール・フランクリンとヴィクター・ヌニェスです。ロジャー・コーマンとの仕事を通してカールと出会った当時、彼はアメリカン・フィルム・インスティテュートのフェローで、彼のおかげで私は1992年、28歳の時にアメリカン・フィルム・インスティテュートに入学することができました。私がカールから学んだのは自信を持つこと、ルーズであること、そして大胆不敵であることです。監督になる前のカールはすばらしい役者でもあったので、彼のキャリアの歩み方にも共感していたんだと思います。そしてもう一人、私の人生を大きく変えてくれたのがヴィクター・ヌニェスです。彼はとても小さなクルーを率いて映画を撮っていて、カメラも自分で回してました。また、彼は映画監督として非常に文学的な志向を持っていて、私が演じるキャラクターの作中では描かれていないバックグラウンドについて、とてもたくさんの話をしてくれました。そうした脚本の書き方や映画の作り方について、私がヴィクターから学んだことはとても多いです。私はヴィクターと仕事をしたことで役者業をやめて監督になることを決意しましたが、皮肉なことに彼との『Ruby in Paradise』(注:日本では劇場未公開。『ディープ・ジョパディー』という邦題でソフトがリリースされた)がきっかけとなって役者業のオファーがこれまで以上に増えるようになりました。そのうちの一人がスタンリー・キューブリックです」
――あなたは昨年、「Variety」誌の現役100人の映画監督による「歴史上最も偉大な映画100作品」という企画で、キューブリックの『2001年宇宙の旅』(68)についてのエッセイを寄稿してました。そのエッセイも大変興味深く読ませていただいたのですが、キューブリックとの交流についてなにかエピソードを教えていただけませんか?
「スタンリーは『Ruby in Paradise』を観て、その4年後に電話をくれて、『私と一緒に「アイズ ワイド シャット」を作らないか』と誘ってきました。自分の心はもう役者業にはなかったのですが、スタンリーのオファーを断れるわけがありません。もっとも、私は18か月間に及んだロンドンでの撮影に拘束されたにもかかわらず、たった3シーンしか出てないんですけどね(笑)。カールやヴィクターのような私が一緒に仕事をしてきた優れた監督たちがそうであったように、スタンリーはとても礼儀正しくて魅力的な人物でした。映画監督は、役者やスタッフの保護者ではありません。映画の撮影現場では、それぞれの持ち場にいる人間がみんな自分自身の役割に十分な自信を持ち、全体のプロセスに不安を抱くようなことがあってはならないのです。18か月間に及ぶ撮影の間、スタンリーは私がどんな質問をしても丁寧に答えてくれたし、映画監督としての心得についてたくさんのことを教えてくれました。私がアメリカン・フィルム・インスティテュートで映画監督になる準備をしていることを知っていたスタンリーは、私を編集室に招き入れて、編集中の『アイズ ワイド シャット』のラッシュを毎日のように見せてくれました。それと、実は最初の監督作品『イン・ザ・ベッドルーム』の脚本は、『アイズ ワイド シャット』の撮影期間中にロンドンで書いたものなんですよ」
――それだけ空き時間がたくさんあった(笑)。
「その通りです(笑)。スタンリーはその脚本を読んでくれて、私にいくつかアドバイスをくれました。それは自分にとって信じられないほど大きな、想像を超えるスリリングな時間でした。そう、だから一緒に仕事をする機会を得た監督たちに関しての話をするなら、私はとてもとても恵まれていたと言えるでしょう」
――もう一つ、自分が目を通した海外のメディアでのインタビューでもあまり触れられていなかったことでお伺いしたいのは、『TAR/ター』においてとても大きな貢献をしている音楽担当のヒドゥル・グドナドッティルについてです。HBOのテレビシリーズ「チェルノブイリ」の音楽を担当したことで映画界において注目を集めるようになったグドナドッティルにとって、本作は単独で劇伴を手掛けた映画作品としては『ジョーカー』(19)に続く2作目となりました。
「私は何年も前からヒドゥルの音楽の大ファンだったので、彼女が『チェルノブイリ』や『ジョーカー』の音楽を担当する以前から知ってました。ソロ・アーティストとしてリリースした作品も愛聴していて、映画での仕事についても、彼女がヨハン・ヨハンソンと一緒にドゥニ・ヴィルヌーヴの作品を手掛けるようになったころからとても気にしてました。それと、『TAR/ター』の製作において私はほぼ完全に自由を手にしていたのですが、出資してくれたヨーロッパのスタジオからの唯一の条件が、アメリカ人のスタッフは私だけにしてほしいということだったんです」
――だから役者も含めて、ほぼスタッフがヨーロッパ人で固められていたんですね(編集部注:ケイト・ブランシェットの国籍はオーストラリア)。
「そうです。私は過去の2つの監督作の音楽ではトーマス・ニューマンと組んできて、彼はいずれの作品でもすばらしい仕事をしてくれましたが、今回はヨーロッパの作曲家、それもできれば撮影場所であるドイツの作曲家と組んでほしいと言われたんです。そこで調べてみたら、幸運にもヒドゥル(国籍はアイスランド)がベルリンに住んでいることがわかりました。ただ、一つ気がかりだったのは、彼女はちょうどその時、『ジョーカー』でアカデミー賞を受賞したばかりだったのです。私は彼女のエージェントに電話をして『もっとギャラのいいオファーがたくさん舞い込んでいるだろうけど、なんとか彼女に脚本だけでも読んでもらえないか』と頼みました。結果はご覧の通りです。
私はヒドゥルと初めて会った最初の5分で、彼女がどれだけ気高いアーティストであるかを理解しました。信じられないことに、彼女は『ジョーカー』での成功のあとにほかの仕事はなにも受けず、14か月もの間『TAR/ター』の仕事だけに専念してくれました。これは一般的な映画音楽の作曲家としてもあり得ないことです。ヒドゥルと私は、ベルリンで初めて会ってからすぐに、他のどのスタッフと合流するよりも前に一緒に仕事をするようになりました。脚本を読んできてくれていた彼女は開口一番、『さあ、仕事に取り掛かりましょう』と言ってくれたんです。通常、映画音楽の作曲家は作品がほとんど完成したあとに、2、3か月で音楽を仕上げていきます。なので私は『いや、まだ仕事には取り掛かってもらえないんだ。映画を作るのはこれからだから』と彼女に言いました。すると彼女はこう言うのです。『あなたの脚本はここにある。だから、それに従って音楽を作っていきましょう』。そこから、私は何時間も何時間もこの映画に関するすべてのことについて彼女に話し、この作品に相応しい音楽のフィロソフィーについて話し合いました。そこで私たちが求めたのは、観客が意識をしなければほとんど感知することができないような音楽でした。そのために、彼女はとてつもなく時間がかかる作業を必要としました。『TAR/ター』は音楽についての映画でもあるので、そこには最初からマーラーやバッハの音楽、そして彼らの曲を演奏する様々な楽団の音楽が存在しています。でも、その底で常に流れている音楽、さらにはどんな微かな音響も、すべてヒドゥルによるものです」
――観客が意識さえしないような音まで作っていったということですね。
「そうです。ヒドゥルに『このキャラクターの内なるテンポはどういうテンポなのか?』と尋ねられました。私は正直に『それがどういう意味なのかよくわからない』と答えました。すると彼女は私に『このシーンの脚本を執筆していた時、どんな音楽を聴いてましたか?』と訊いてくるんです。それで、私はいくつかの楽曲を彼女に渡しました。彼女は脚本とその楽曲をヒントにキャラクターのテンポを探し当てて、ロバート・エイムズとロンドン・コンテンポラリー・オーケストラの奏者たちをベルリンに呼び寄せて、音楽を作っていきました。それによって、『TAR/ター』の撮影現場では、彼女が作ったばかりの音楽を流して、それをそのまま同録することができました。役者たちはヒドゥルの音楽を耳にしながら、それぞれのキャラクターのテンポに合わせて身体を動かしていったのです。ただ、ヒドゥルは映画に自分の痕跡を残して、それを誰かから指摘されることを好みません。彼女は常に作品の中で迷子でいたいと願っていて、自分をなるべく人から見られないようにしたいと思っているんです。なので、私は彼女のことについて少ししゃべりすぎたかもしれません(苦笑)」