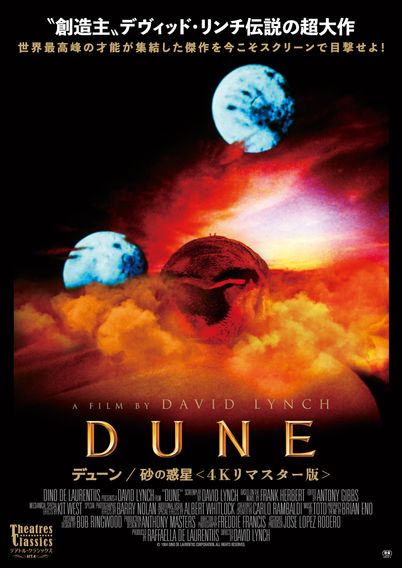【追悼】デイヴィッド・リンチよ安らかに…難航したデビューから長編遺作となった180分の怪作まで、“映画監督”としての経歴を振り返る
『マルホランド・ドライブ』の成功の後、リンチは会員制サイトを立ち上げ、インターネット上で短編作品を発表していく。多くのファンが次の劇場公開作を期待するなかで、リンチはたまたま近所に越してきたローラ・ダーンのために短い脚本を書き、思い付いたアイデアを撮影してはまた次のアイデアで撮影するということを繰り返していく。
全体の脚本がない状態で2年半かけて撮り続けた映像を集約させ、会員制サイトで公開していた作品の断片も流用しながら完成したのが、180分にも及ぶ怪作『インランド・エンパイア』(06)だ。大まかに言えば、ハリウッドで暮らす女優が未完のポーランド映画のリメイクの主役に抜擢され再起を図ろうとするものの、やがて現実と映画の区別がつかなくなり迷宮へと迷い込むというストーリーの作品だ。
先述のように、リンチが好きなように好きなものを撮るというあまりにも自由な製作過程ということもあり、『マルホランド・ドライブ』以上に難解で複雑怪奇な作品になっているのだが、不思議なほどに中毒性のある作品だ。わからないけれど自然と惹き込まれてしまい、わからないことを楽しんでしまう。そしてなんといっても、ニーナ・シモンの「Sinnerman」に合わせて人物が当て振りで踊るエンドロール。最後にタイトルが出て、映画館の場内が明るくなった瞬間に味わった達成感は計り知れないものがあった。
その後リンチは長編映画を手掛けることはなく、10年以上経ってから長編映画監督からの引退を宣言した。つまりあのエンドロールが、劇場体験として我々に提示される最後のショットになることがその時に確実なものとなり、結果的に本当にそうなってしまった。それでも、映画監督の幕引きとして、あれほど完璧なものは後にも先にもないだろう。同作で名誉金獅子賞を受賞した際、記者会見でのリンチの言葉がすばらしいので、共有しておきたい。
「どんな映画も未知の領域に誘ってくれるものだ。だが、観る者は直感力を駆使することを恐れてはいけない。とにかく感じ続けること。内にある知識を信じることだ。シネマはかくも美しい言語だ。あなた方(記者たち)には言葉の才能があるだろう。しかし、シネマは言葉を超えたものだ、シネマと音楽は似ていて、美しく知的な旅のできるすばらしいものだ。言葉なしに語りかける。だから、違う世界を開き、ぜひ体験してほしい」(『インランド・エンパイア』劇場パンフレットより引用)。
晩年には自身の代表作である「ツイン・ピークス」の25年ぶりの新シーズンとなる「ツイン・ピークス The Return」を手掛けたり、スティーヴン・スピルバーグ監督の『フェイブルマンズ』(22)ではクライマックスにジョン・フォード役として出演していたリンチ。哀悼の意を表すよりも、映画というもののおもしろさと可能性、そして美しさを教えてくれたことに、『フェイブルマンズ』の主人公の言葉を借りて「Thank you」と一言だけ伝えたい。
文/久保田 和馬