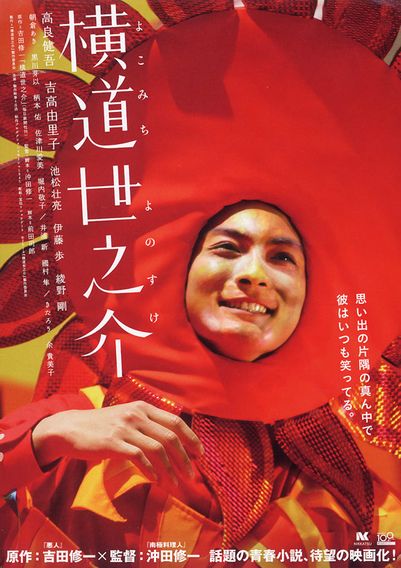吉田修一×綾野剛が白熱対談! 一瞬を永遠にする『楽園』はどこにある?
――瀬々敬久監督は、「犯罪小説集」の文庫本の解説で「吉田修一氏の小説には登場人物たちの生きる空間がいつも丹念に描かれている。以前から、そこに強く惹きつけられてきた」と綴ってらっしゃいましたね。瀬々監督は濃密な人間描写が高い評価を得ている演出家ですが、監督の演出にどのような印象をお持ちですか。
吉田「僕の好きな監督の条件って、僭越な言い方になるかもしれませんが映画で“永遠性”を表現できる方なんですね。これまで瀬々さんはそれを、形を変えていろんな作品で撮ってこられた稀有な監督だと思っています。綾野くんは『64-ロクヨン-』に出演されていましたが、瀬々組はどうでした?」
綾野「半分、言葉のアクション映画みたいなところがあって、セリフの応酬があったり、肉体的に(佐藤)浩市さんが引っ張ってくださって、役者たちが率先して“最前線”にいる感じでした。それと比べると、今回はいつも瀬々さんが撮影の最前線に立とうとしていた気がします。台本を持った後ろ姿に異様な覚悟が漲っていて、僕は瀬々さんが地ならしをしてくれた空間に安心して身を任せ、たゆたうことができました」
吉田「撮影後、こうやってお会いして、いろいろと話を伺っていると、本当に豪士に会っているような錯覚をしてしまって(笑)。いま言われた“たゆたう”という形容もそうですが、あの時そんな心境や状態だったのかと、とても新鮮です」
綾野「瀬々さんが探し抜いて選び、そして、瀬々組のスタッフが作り上げたロケーションの環境自体がたゆたっていたんですよね。暑い真夏のゆらぎも加わって、世界がたゆたっていたというか。登場人物は皆、まるで幻のように現れて、また幻のように去ってゆく」
吉田「脚本に関して言えば半分くらいがオリジナルで、杉咲花さんが演じられた、12年前に失踪した少女の姿を最後に見た同級生の紡(つむぎ)のシークエンスが大きく膨らませてあって、そういったことも含めて瀬々さんの色が強く出ていて嬉しかったです。僕は前から監督の大ファンで、自分の原作が“瀬々色”に染まるのを期待していたのですが、なかでもY字路のラストシーンが大好きで!映画的なカッティングで主要登場人物が一瞬、クロスするじゃないですか。あの一瞬が各々の人生を決めてしまうさまが見事に捉えられていた。プロットが脚本へと変わっていく段階から、『このシーンは実にすばらしいなあ』と思っていましたが、完成作を観たら想像したものをはるかに超えていて、圧倒されました」
綾野「良かったです。瀬々さんの作品って、尖ってはいるんだけどもバラエティに富んでいて、全部のテイストが違うんですよね。例えば原作があれば、敬意をもってアレンジを施し、ご自分の作家性も加味させてコラボレーションしていく。瀬々さんは役者さながらに、カメレオンのごとく変容していく監督だと思います。そういえば豪士が自分の母親に、『俺を捨てるの?』って言葉を投げかけるシーンがありますが、撮影が終わったあと、ぜんぜん瀬々さんが目を合わせてくれなくて、もしかしたら良くなかったのかもと思っていたら、ちょっと時間が経ってから『あんな芝居はいままで見たことがないよ』と言ってくださった。もうベテランの域に達しているのに、そこまで真っさらな状態、つまり、過去にやってきたことを勇気を持って捨てて現場に臨んでいることが分かって感動したんです。そういう方なんですよ、瀬々さんは」
本作は、被害少女と事件直前まで一緒だった親友、贖罪に苛まされ、それぞれの不遇に共感して豪士とも心を通わす湯川紡、さらにはY字路に続く集落で村八分になり、孤立を深め壊れていく田中善次郎(佐藤浩市)など、寄る辺なき人々にスポットライトを当てている。綾野は対談中、「映画を観て僕は、紡が“楽園”という名の希望のように受け取りました」と語った。