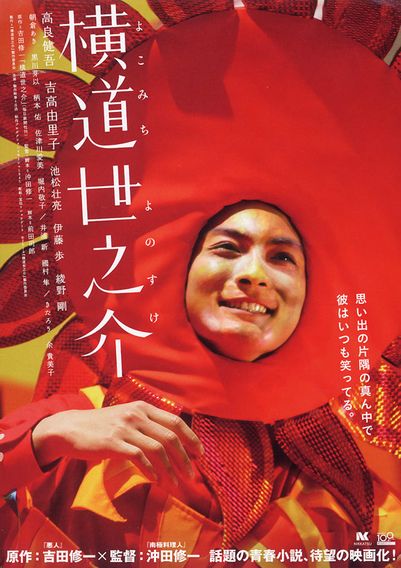吉田修一×綾野剛が白熱対談! 一瞬を永遠にする『楽園』はどこにある?
――原作の「犯罪小説集」から『楽園』へ。大胆なタイトルの改変ですが、どのようなお考えで進められたのでしょう。
吉田「“タイトル会議”に呼ばれたんですよね」
綾野「どれくらい候補があったんでしたっけ?」
吉田「100個ぐらいアイデアがあって。でも、話し合いになる前に、瀬々さんが『“楽園”で行きたいんですけど』っておっしゃって、監督がやりたいことを一言でまとめるとすればこれしかないんだろうな、と直感的に、胸にストンと落ちたんです。僕ね、幸せって長さではなくて密度だと思っていて。小説では豪士、紡、善次郎、遺族や町の人々が引きずってきた“時間”を書こうとしたんですけど、それが映画には確かに映っていました。一瞬が永遠になること。その一瞬を“楽園”と呼ぶならば、本作は楽園にたどり着けなかった人たちの物語では決してない気がします」
綾野「いま修一さんがおっしゃったことを、同じように感じていますし、豪士にとっての“楽園”ってなんだったんだろうと考えると、新たな朝を迎える、明日が来ることだと思い、僕は豪士という役を生きていたんです。不条理にも事件で亡くなってしまった少女にはその明日が来ない…豪士は明日が来ることへの恐怖や喜びと向き合いながら、今日を噛みしめて生きていた」
吉田「なるほど。こうやって映画にしてもらったものを観て、会話をすると、執筆中には気づかなかったことにたくさん気づかせてもらえるんですね。綾野くんは『世の中には抱きしめてあげなきゃいけない人がたくさんいる』ともおっしゃっていたじゃないですか。それを聞いた時、『そうか、この短編集を書きながら、なにか気になり、見つけたいと思っていたのはそれだったのか』と発見できたんです。今日も話ができて良かった!」
綾野「こちらこそです。撮影現場でもそうでしたが、完成した映画を観て、登場人物みんなを愛おしいと思ったんです。特に、豪士と紡、善次郎のことを。哀しみと切なさがループしているような境遇で生きていて、彼らこそ抱きしめられなきゃいけないなって。同時に、この世にはリアルに、人肌で包まれ、抱きしめられるべき人たちがたくさんいるんだということを改めて痛感してほしい。とても苦しい、胸に刺さるような事件が現実でも多いなか、僕は今後、必ずや機会があればそういう人たちを抱きしめようと心に誓いましたし、この作品をご覧になって、そう感じてくださる方がひとりでも増えたらという願いを込めて、この作品を伝え届けていきたいです」
取材・文/轟 夕起夫