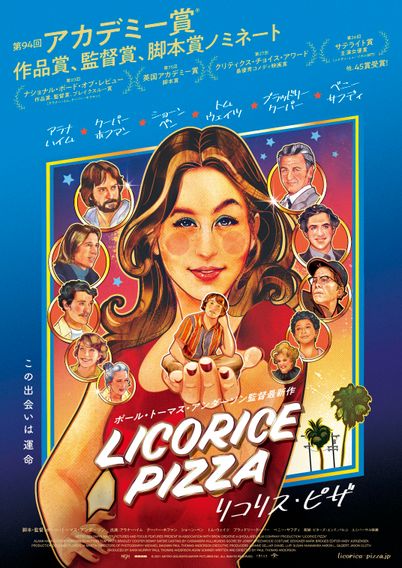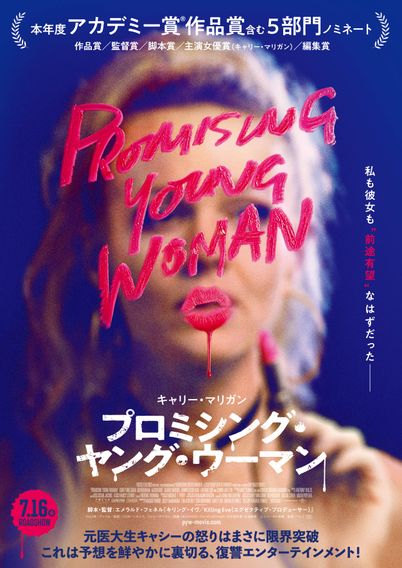映画は死なない。でも、我々が夢中になってきた ハリウッド映画はもう存在しない。「ハリウッド映画の終焉」著者・宇野維正、1万字インタビュー
「1本の作品で完結していて2時間前後で終わる、それが自分が一番夢中になってきた映画のフォーマット」
――『プロミシング・ヤング・ウーマン』(20)、『ラストナイト・イン・ソーホー』(21)、『カモン カモン』(21)、『フェイブルマンズ』(22)、『Mank/マンク』(20)、『リコリス・ピザ』(21)、『TENET テネット』、『TAR/ター』。言われてみると、本書ではフランチャイズ作品ではなく、原作ものでもない、オリジナル脚本の作品を多く取り上げてますよね。
宇野「だって、映画ってそういう作品が一番興奮するじゃないですか。さっきの“ハイコンテクスト”の話ともつながりますが、1本の作品で完結していて2時間前後で終わる、それが自分が一番夢中になってきた映画のフォーマットだから。シリーズ30作目の新作だとか、3部作の真ん中の作品だとか、Apple TV+で配信される前に2週間限定で劇場公開される4時間の映画だとか、そうやってハリウッド映画はこれからもフォーマットを変えて生き延びていくんでしょうけど、現実として、1本の作品で完結していて2時間で終わるハリウッド映画は絶滅状態にあるわけですよ。
“よく知ってるキャラクターがスクリーンで活躍する姿を見るのが一番楽しい”という人もいるでしょうし、その楽しさを否定するつもりはないです。でも、スクリーンで初めて出会うことになるキャラクターが、2時間の物語を経て、心理的にも地理的にも最初とはまったく異なる場所にいる。そういう映画を観ることで、映画館に入る前と出た後で世界の景色が変わって見える。それが狭義の“映画”だとしたら、いまそういう作品をハリウッド映画の予算規模で撮れているのは、本当に一握りのスーパーエリート監督だけだし、そんな監督たちも“これが自分の最後の映画になるかもしれない”と思いながら作品を撮ってるわけです。そりゃあ、自分の幼少期を題材にしたくもなりますよ」
――本書では、映画とハッシュタグ・アクティビズムが結びつくことの問題点などについても、章を横断して何度も触れられています。
宇野「アイデンティティ・ポリティクスの問題とファンダムの問題は、ハッシュタグ・アクティビズムを武器としている点において同じです。最も象徴的なのは、過去のツイートが発掘されたことをきっかけにディズニーがジェームズ・ガンをキャンセルしたことと、ワーナーがザック・スナイダーの『ジャスティス・リーグ』ディレクターズカット版を求めるファンの声に答えて作品を実現させたことですが、自分は本書の中で、かなり強い言葉でそれらの運動と当時のメジャースタジオの対応を批判してます。その理由は本を読んでもらえればわかってもらえると思いますが、一つ言うならそれらが起こったのはトランプ政権下、つまり2017年から2021年にかけてのことで、それは決して偶然ではないんですよね。これは本書の主題ではないし、まだ時期的に早すぎるかもしれませんが、#MeToo運動に関しても、その成果については評価しつつも、そうした視点からの個別の検証が今後はあってしかるべきだと考えてます。
だって、明らかにおかしいじゃないですか。自分の過去の発言を掘り出されるのが怖くて、アカデミー賞の司会を誰にオファーしても断られるという時期が何年も続いたんですよ。後世から見れば、禁酒法時代とか赤狩り時代とかと並んで『なんて奇妙な時代だったんだ』ということでしょう。現象面においては、左とか右とかの政治信条と関係ないどころか、その行動原理はまったく同じ。ジェームズ・ガンのキャンセル騒動のように発火させたのが右で、それを左がさらに炎上させるようなことまで起こってきました。『TAR/ター』では、ナチスにちょっとでも親和的だった人間を業界から排除する“非ナチ化”運動が、ドイツのクラシック界の業界政治にいかに利用されてきたかということに触れてましたけど、あれは明らかに現在のキャンセルカルチャーのアナロジーと捉えるべきでしょう」
――その時代はまだ続いてる?
宇野「どうでしょう。この本がソーシャルメディアで叩かれたらまだ続いてるってことなんじゃないでしょうか。真面目な話、そのくらい覚悟して本を書いてますよ。でも、是枝裕和監督の『怪物』やディズニーの実写版『リトル・マーメイド』のソーシャルメディアでの語られ方を見てると、暗澹たる気持ちになってしまいますね」
――そういうソーシャルメディアの空気が変わることは、今後あるんでしょうか?
宇野「その前にソーシャルメディアの価値がどんどん下がっていくんじゃないですか? 実際、特にTwitterは嫌気がさしてやめていった人も多いじゃないですか。北米でも有力な批評家ほど、いまでは課金制のブログやポッドキャストに閉じこもってます。自分はネット上ではポリコレという言葉を絶対に使わないようにしてるんですが、ある作品を観て『これ政治的にちょっとおかしくない?』って指摘するのは全然いいと思うんですよ。でも、ここ数年起きていることって、政治的な理由から作品をことさら強い言葉で全否定したり、ある種の不買運動に駆り立てたり、その作品を支持している人を攻撃したりと、作品を観てない人も巻き込むところまでがセットだった。それは、はっきり言いますが、2017年以降の一部の人たち――そこにはファンダムも含まれますが――の成功体験がもたらした負の側面です。だから、とりあえず指摘だけするところまで一旦戻ろうぜ、と思いますね。あと、作品を観てない人の言葉は一切相手にしないこと」
――ひとえに、映画に失礼じゃないかっていうことですよね。
宇野「そうです。映画が自分にとって大事なものだから怒ってるわけで、映画がなにかのための道具や武器だと思ってる人にはなにを言っても通じないのかもしれませんが」
――『ROMA/ローマ』のように文中で触れているものもありますが、16本に入り切らなかった作品はありますか?
宇野「『TENET テネット』以降、つまりコロナ禍以降の2020年代の作品というのを、この本では縛りとしました。でも、よく考えたら2020年代に入る直前の2019年ってめちゃくちゃ豊作で、『ジョーカー』『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』『フォードvsフェラーリ』『パラサイト 半地下の家族』、そのあたりの作品って北米公開は全部2019年なんですよね。そういう話は、6月18日に大阪で開催する刊行記念イベントで話そうかと」
――ほとんど配信プラットフォームで観られる作品ばかりなので、予習や復習も容易にできますね。
宇野「そうです。こんな便利な環境に生きてるんだから、それを最大限利用しない手はない。配信プラットフォームって、プラットフォームのアルゴリズム自体がそう仕向けるということもあって、つい新作ばかり追ってしまうじゃないですか。でも、かつてレンタルビデオ屋で旧作の棚を漁っていたように、ちょっと前の作品を観るきっかけがもう少し増えるといいと思うんですよね。新書というフォーマットにしたのも、理想としては、出張前のビジネスパーソンが新幹線のキオスクで買うみたいな感じで、普通あまり映画を観ない人にも届けたかったからで。いまは、キオスクで新書を買う人なんてあまりいないと思うけど(笑)」
――タイトルに“終焉”とあるので、ちょっと寂しいイメージもありますが、そこには希望もあると?
宇野「少なくとも、オリジナル脚本の2時間のハリウッド映画ということに関して言うなら、希望はないですね。やっぱり、自分は映画の原体験がスティーヴン・スピルバーグの世代ですから。スピルバーグだって続編作ってるじゃないかと思われるかもしれないけど、いや、全部公開時に1作目から観ちゃったんだよと(笑)。あの興奮を追い求めて、ずっと映画を観ているようなところはある。だから同じ年のポール・トーマス・アンダーソンとかクリストファー・ノーランとか、ちょっと年上のドゥニ・ヴィルヌーヴとかクエンティン・タランティーノとか、あの年代の人たちが現在の映画に対して抱えている諦念というのが、めちゃくちゃわかるんですよ。まあ、ノーランはまだ戦ってますけど」
――タランティーノの新作にして最後の映画のタイトルが『The Movie Critic』というのも象徴的ですね。
宇野「本当にそうですよ。そのニュースを最初に見た時は『遂にトドメを刺しにきたか』と思って寝込んじゃいました(笑)。僕自身、書き手というかしゃべり手というか、ジャーナリストとしてはまだ希望は持ってますけど、Movie Criticという面では、もうこれからずっと死ぬまで撤退戦を強いられていくんだろうなって覚悟してます。完全にダンケルク状態ですよ」
――まあ、ノーランは『ダンケルク』の後も精力的に新作を撮っているので…。
宇野「やりたいことはたくさんありますよ。ハリウッド映画と違って、日本映画ってまだまだ可能性があるということがここ数年で見えてきたと思うので。そこに少しでも貢献できないかなって気持ちもあるし。あともう一つは、海外のテレビシリーズですね。テレビシリーズって、もうかれこれ15年くらいピークが続いてきましたけど、誰も歴史としてちゃんと書き残してないじゃないですか。ニーズがあるかどうかは別にして、テレビシリーズの分野はほとんど手つかずのまま残っている。あとは自分の書き手としての価値を高めて、そこにニーズをどう作るかということです」
――そういえば、3年前の連載『映画のことは監督に訊け』第1回で三木孝浩監督に「日本のティーンムービーを海外に持っていったら絶対おもしろいことになりますよ」っておっしゃってましたが、昨年、新作の『今夜、世界からこの恋が消えても』 が韓国で大ヒットを記録しましたよね。
宇野「そう。そのくらいの先見の明はあります。だからこんな時代になっても、この仕事を続けてられるんです。はっきり言って、日本映画界に韓国映画のリメイクとかやってる暇なんてないですよ。アニメーション作品は既に結果を出しまくってますが、実写作品もある程度のクオリティさえ担保できれば、特に広大なアジアのマーケットにおける可能性は大いにあると思います。『ハリウッド映画の終焉』は、日本やインドのような21世紀に入ってからもまだ映画をたくさん作ってる国にとって、チャンスでしかないです」
取材・文/下田桃子(編集部)
宇野維正の「最重要作品10本」
6月18日(日) OPEN / 17:00 START / 18:00
観覧:前売 ¥2,000 / 当日 ¥2,500
配信:¥2,000
会場:梅田 Lateral(大阪府大阪市北区堂山町10-11 H&Iビル 2F)
チケット予約など詳細はこちら