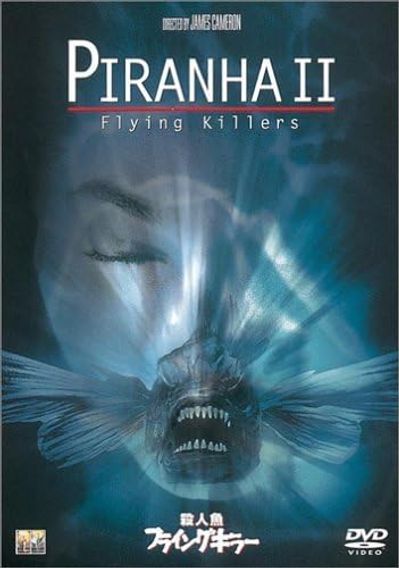「一分の隙もない」「没入感は前作以上」『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』はやっぱりすごかった!
「社会にはじかれて“自分は周囲とは違うかも”と思い悩む、共感しやすいテーマがある」(下田)
佐藤「前作のヴィランで死んだはずのクオリッチ大佐(スティーヴン・ラング)がアバター化して、より手強い悪役となって出てくるというのもおもしろかったし、同じく前作で死んだはずの女性科学者役のシガーニー・ウィーバーが、その娘キリ役で再出演しているのも前作のファンにはうれしいですよね」
西川「大佐のアバターが大佐の遺言ビデオを見ているシーンは『トータル・リコール』みたいでニヤッとしました。キリの父親が誰だかわからず、彼女は何者なのか?というところにも興味を惹かれますね」
下田「戦争孤児として家族と暮らす人間の少年スパイダー(ジャック・チャンピオン)もそうですし、キリやジェイクの実子など、子どもたちが意外に大きな役でしたよね。ジェイクとネイティリの家族の話と聞いていましたが、彼らが想像以上に大きな活躍をするので、ある意味、ジェイクらの次世代の物語でもあると思います。私は、1作目はとてもアメリカ的なストーリーだと感じたんですよ。傷ついたアメリカ兵が、知らない文化圏で居場所を見つけていく、というような、『ダンス・ウィズ・ウルブズ』的なフロンティア映画でしたよね。そういう点では、今回はより普遍的なドラマになっていると思います。特に子どもたちのドラマは、社会にはじかれて“自分は周囲とは違うかも”と思い悩む、共感しやすいテーマがありますよね」
西川「出来のいいジェイクの長男のネテヤム(ジェームズ・フラッターズ)に対して、次男のロアク(ブリテン・ダルトン)は父に認められず、なにかにつけて邪見にされますからね。次男あるある的な部分は共感を得やすいし、多くの観客の目線もそこに行き着くんじゃないでしょうか」
「父親としてはジェイクにすごく共感した」(佐藤)
佐藤「僕は父親としてはジェイクにすごく共感しましたね。ネイティリに、息子たちに対する軍人気質な厳しさを責められたりするけれど、死ぬかもしれない自然の厳しさのなかで子どもを育てるんだから、そりゃあ多少は厳しくしないとダメだよなあ、とか(笑)。興味深かったのは、ジェイクとネイティリの子どもたちは、要は人間とナヴィのDNAが混じり合っているわけじゃないですか。それによって、肉体的な混血の特徴を海の部族の子どもからバカにされたりする。そういうコミュニティ感は、アメリカ的だなと思いましたね。仲直りしたと見せかけて、さらにイジメるシーンもありましたが、そういうところなんてメチャクチャ、アメリカっぽい」
西川「ティーンエイジャーのドラマとしては、アメリカの学園モノにも通じますね。幅広い年齢の客層にシンクロする物語と言えそうです」