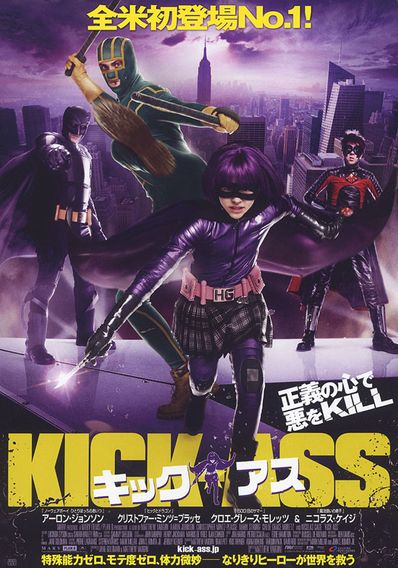独占取材!リリー・フランキーが『バビロン』の自由を貫く姿勢に共鳴「ものづくりをしている人が観たらショックを受ける」の真意とは?
「みんなで一つのものを作っている時に、なにかグッとくる瞬間がある」
数々の名監督とタッグを組み、俳優としても引っ張りだこになっているリリー。ハリウッド黄金時代にそれぞれの部署が力を合わせて映画製作に打ち込む姿が描かれた本作は、リリー自身も映画業界に身を置いているからこそ、心を動かされる部分も多かった様子だ。
リリーにとって、映画製作の現場で醍醐味を感じるのはどのようなことだろうか。リリーは「やっぱりなにかあるんですよね」と切りだし、「みんなで一つのものを作っている時に、なにかグッとくる瞬間がある。その一瞬を感じた時に、映画っていいなと思う。毎回感じられるわけではないですし、逆に言えば、それを感じてしまった人は、なかなか映画の魔法から解き放たれることができない」としみじみ。「本作を観ていても、100年以上前から映画の魔法にかかってしまった人がたくさんいるんだなと思うし、そういう人たちってとても熱いものを持っている。だからこそ映画業界を題材にした映画って、あまりハズレがない気がしています」と持論を述べる。
本作は、サイレント映画からトーキーへと移行していく、映画の歴史を目にすることができる作品でもある。異様な熱気に包まれたハリウッド黎明期を再現するうえでは、チャゼル監督が過激な描写にもチャレンジしている。
リリーは「裸や性表現、ドラッグなど、いまの時代では制限されるような表現が、本作には気持ちいいくらいに詰め込まれていました。たしかに、いま禁じられているものが当たり前に存在していた時代を描くうえで、エロやグロを出すことに及び腰になっていては、描写力が落ちてしまうはず。僕も少なからず映画の仕事をさせてもらっていて、いろいろな制限のなかで表現をしている部分もあるので、『この映画は制限を気にしていない。むしろ逆手に取っているんだ』と、観ていても小気味よかったですね」とにっこり。
「あらゆる軋轢のなかで表現に挑んでいるからこそ、自由を貫こうとしている『バビロン』はとても痛快」
「本作の登場人物たちは、映画の時代が変わる瞬間を目の当たりにしている人たち。サイレントからトーキーに変わって、テク二カラーが使われるようになったりと、映画の技術は強烈な変化を遂げてきました。一方、いまを生きる僕らは『こういう表現をしてはいけない』と映画が不自由に変化していくのを見続けているのかもしれません。あらゆる軋轢のなかで表現に挑んでいるからこそ、自由を貫こうとしている本作はとても痛快で、なんだか元気をもらいました。スカッとしましたよ」と刺激的な時間になったという。
映画愛に満ちた本作に触れると、チャゼル監督が先人たちから映画づくりへの情熱を受け継ぎ、彼らに尊敬を抱きながら邁進していることが伝わる。リリーは「日本の映画監督など、ものづくりをしている人が本作を鑑賞したら、『こんな映画を撮れるようになるには、まだまだ道のりが遠いな』とショックを受けると思う」とコメント。「飛行機が落ちたり、ビルが倒れたり、いかにもお金がかかりそうなアクション描写にお金をかけているのではなく、みんな『映画が好きだ』という想いで集まって、人間の滑稽な営みを描くことに潤沢な予算をかけているような映画。僕はそのことにとても感動しましたし、うらやましさも感じました。映画って本来そうあるべきものなのかなと思っています。こんな映画をつくったあとに、一体なにをつくるのか。すでにチャゼル監督の次回作が楽しみになっています」と、『バビロン』からまぶしさを受け取っていた。
取材・文/成田おり枝
イラストやデザインを手掛けるほか、文筆、写真、作詞・作曲、俳優など、多分野で活動。2006年本屋大賞を受賞した初の長編小説「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」は、220万部を超えるベストセラーとなり、舞台やドラマ、映画化も果たした。ほかオリジナル絵本「おでんくん」の出版や、俳優としては『ぐるりのこと。』(08)、37回日本アカデミー賞優秀助演男優賞を受賞した『そして父になる』(13)、『万引き家族』(18)など、多くの映画、ドラマなどに出演。