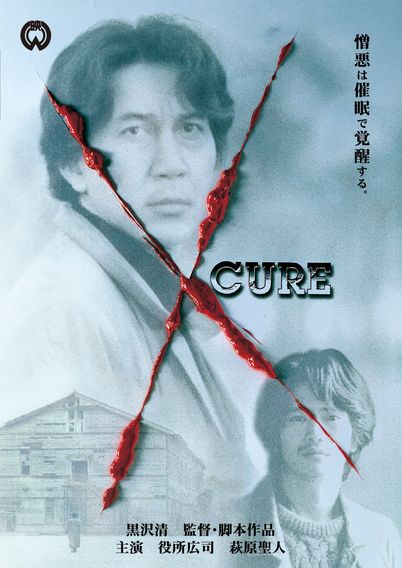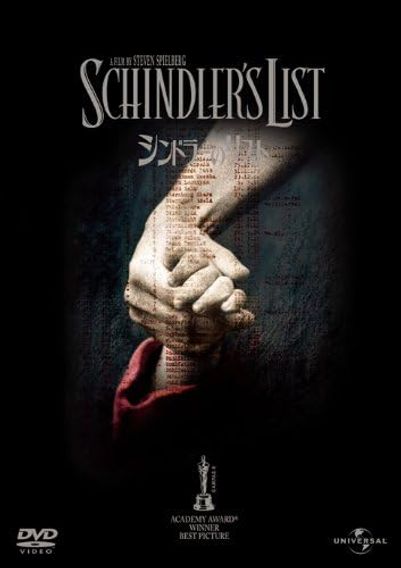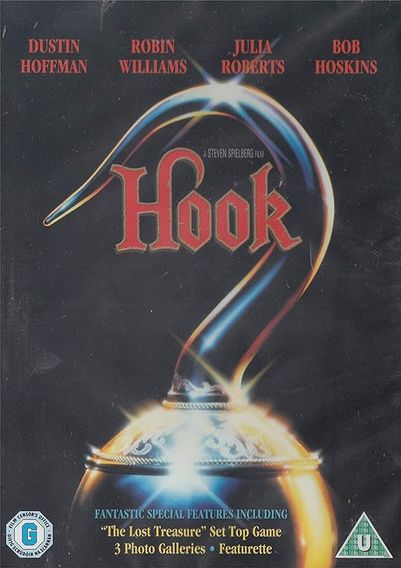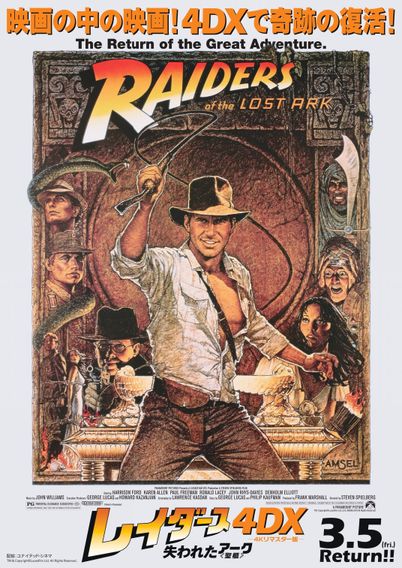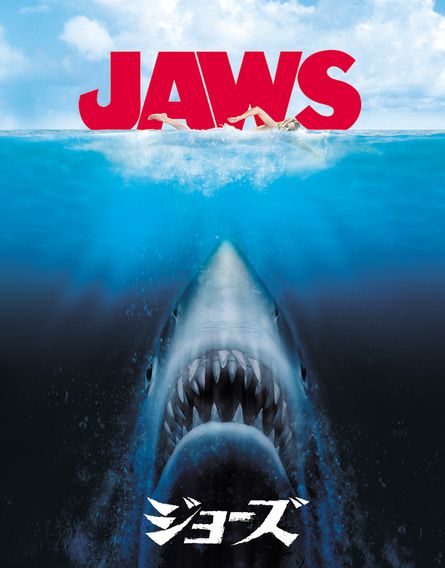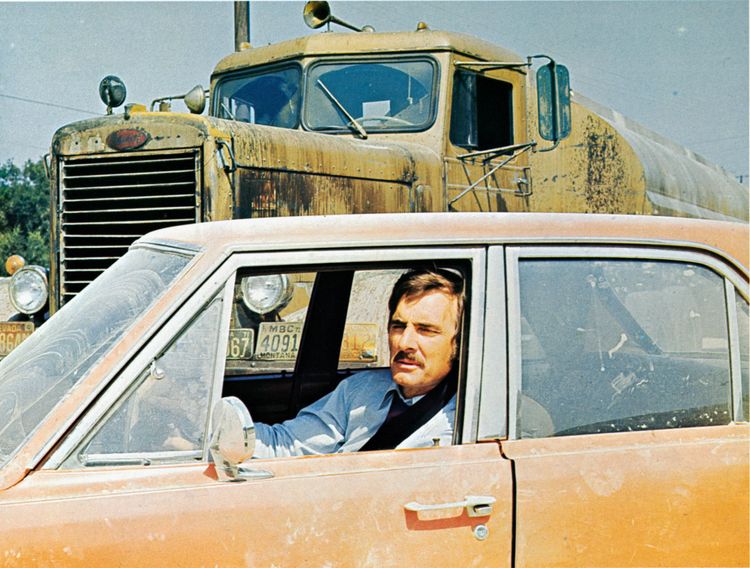黒沢清がひも解く、スティーヴン・スピルバーグのキャリア「いつまでも“巨匠”にならないことが最大の魅力」
「スピルバーグ監督はいつまでも“巨匠”にならない」
最新作『ウエスト・サイド・ストーリー』(21)ではスピルバーグ監督自身も敬愛する名作をリメイクし、カミンスキーと共にキャリア初のミュージカルにトライ。第94回アカデミー賞作品賞にノミネートされるなど成功を収めたことについて黒沢監督は、「一歩間違えると失敗しかねない企画でもある『ウエスト・サイド物語』をとてつもない計算力で処理し、すべてが上手くいっていた作品でした」と、改めてスピルバーグ監督の演出の才力を称える。
「僕自身はミュージカルをやったことがないのでわからない部分も多いのですが、ミュージカル映画の成否は“どうしてそんなところで歌って踊ったりしているのか”という違和感をいかに解消できるかにかかっていると感じています。特に映画は、舞台以上にリアリズムが要求されがちです。そのなかで決闘シーンなど登場人物の生死に関わる時には外側を描かず舞台的に、『アメリカ』のシーンのように歌と踊りがあふれる時には思いっきって外側の現実も巻き込んでいく。感動的ですよね。観る前に勝手に抱いていた不安は、いともたやすく吹き飛ばされてしまいました」。
75歳を迎えてもなお新たな挑戦を続けるスピルバーグ監督の最新作に、大満足の様子で饒舌に語った黒沢監督。「きっと『E.T.』の後、スピルバーグ監督が『これでいいんだ』と思って似たような作品を次々と作っていれば、すぐにでも“巨匠”になっていたかもしれません。でもあえてそうはしなかった。そして、カミンスキーとの出会いを通して“巨匠にならなくていい”という覚悟を持ったからこそ、常に新しいものにチャレンジし、いまの地位を築いていったのでしょう。いつまで経っても“巨匠”にならないこと。それこそがスピルバーグ監督の最大の魅力であり、その姿勢を私自身も忘れずにいたいです」。
「自分は好みや信じるやり方でやっていくしかない」
その言葉通り黒沢監督自身も、スピルバーグ監督と同じように“新たな挑戦”を続けている。3月に発売された乃木坂46の29枚目のシングル「Actually…」で表題曲のミュージックビデオを監督。また、Amazon Prime Videoで2022年秋に配信されるAmazon Originalドラマ「モダンラブ・東京」を手掛けるなど、”映画”というフォーマットにこだわらず、さらに精力的な活動を行っている。
テレビ作品を数多く手掛けていた時代にも、後の日本映画界を賑わす“Jホラー”の源流となる作品を次々と発表。また、WOWOWの連続ドラマとして2012年に製作された「贖罪」、2014年に手掛けた前田敦子のミュージックビデオ「Seventh Code」、NHK BS8Kで2020年に放送されたテレビドラマ「スパイの妻」は、それぞれ映画として再構築され海外の映画祭に出品。海外での高評価を提げて劇場公開もされるなど、まさにその活躍は国境やジャンルはおろか、発表するメディアもボーダーレスだ。
映画界の主要なトピックの一つとして、劇場公開用映画と配信用作品との共存について大きく取り沙汰されるようになって久しいが、黒沢監督は「その両者にこれといって大きな差を感じてはいません」と明かす。「全体の長さや作業の分量は異なっていても、私自身が監督としてやることや撮影現場はほとんど同じです。できたものが映画館でかかるのか、それとも配信なのかレンタル用の映像作品なのか、あまり気にしたことはありません。本当はもっと気にしたほうがいいのかもしれませんが」と小さく微笑む。
そして「スマートフォンで映像を観ている人は、その小さな画面で観ても成立するように作品作りをしていると思います。でも私の場合は逆のアプローチで、もしかしたら小さな画面に向けて作っているものでも、映画館の大きなスクリーンでかかるかもしれないと考えるようにしています。小さい画面だからといって油断をしてはならず、どのように観てもらえるのかはその時次第。なので、自分の好みや自分が信じるやり方でやっていくしかないと思ってやっております」と覚悟を見せる。輝かしい名誉を手に入れ、”映画”に魅了された監督たちの飽くなき挑戦は、いまもなお続いている。
取材・文/久保田 和馬